目次
こんにちは、不動産で明るい毎日を目指す六本木の不動産屋、(株)リビングインで賃貸の契約や入居後の管理を担当している、宅地建物取引士兼管理業務主任者の相樂です。
賃貸マンションだけでなく、分譲マンションも隣人との騒音トラブルは結構相談があります。特に、自宅にいる事が増えた2020年、2021年と電話やテレビ、子供の騒ぎがうるさすぎて、眠れないという方から、「訴訟は出来るのか?」という深刻な相談もありました。

今回の相談は、今年の2月に受けたもので、ご近所トラブルで多い「騒音問題」に悩み、あの手・この手で解決しようとしたものの、全く改善せず、消費者センターにも相談したところ、「裁判をしてはどうか?」と真顔で提案されたという方からのものです。
1.隣人の深夜の電話がうるさく我慢ならない
「安易に裁判して勝てるかどうかも分かりませんし、裁判をするとなると50万ほどかかると言われてしまって・・・。慰謝料を取れればいいんですが、もし勝てなかったら、ただ損して終わるだけと思うと、それは絶対に避けたくて・・・。」
と、相談者様は困り顔でそう仰っていました。詳しく事情を聞くと、港区のマンションに在住の相談者様で、隣人が深夜にベランダで長電話をしているとのことでした。その声が非常に大きく、相談者様の部屋にも聞こえてきて、睡眠を邪魔されるそうで、ストレスが溜まり生活や仕事にも影響が出てしまっている、という深刻な問題でした。
「まず管理会社に相談して、掲示板に告知を貼ってもらって注意を促したんですが、全然ダメで。警察にも立ち会ってもらい、実際に訪問して注意しようと思ったら居留守ですよ。もうね、何度もチャイムを鳴らしたんです。日中は全然出てこなくて、外出してるのかな、と思ったんで、電話中にもチャイムを鳴らしたんです。ところが出ない。
気付かないフリです。逮捕状でも出てりゃ、強制的に踏み込めるらしいんですが、そういうんじゃないから出てくれなければ説得もできないって言われちゃって・・・」
それで、困り果てて消費者センターに相談したら裁判を勧められたという流れでした。「裁判して勝てるなら、裁判したい気持ちが強いんですが、50万はデカイし・・・。これって実際勝てるもんなんですかね?」相談者様は他にどのような機関に相談したら良いかも分からないし、裁判で争っても勝てないならば引っ越しも考えたいということで、住まいのトラブルをこれまで見てきた私たち、アリネットに相談しようと思ったそうです。
2.隣人との騒音トラブルはマンションにはつきもの?

今回のトラブルは、部屋探しの最中、なかなか予測することが難しく、実際に住んでみて初めて明らかになる類のものです。ご近所トラブルの代表格である「騒音」トラブルは、マンションやアパートにはつきものです。なぜなら、賃貸や分譲マンションの隣人や上階の住人たちが立てる音は事前に知ることが困難だからです。
物件の周辺環境に騒音の要素が無いかどうかという点は事前に確認できます。飲み屋街や歓楽街があれば深夜も賑やかですし、路線沿いや環状道路などがあると電車や車の音が気になります。周辺環境の騒音レベルに関してはしっかり調べ、確認することによって「騒音に悩まされる物件」を避けられます。
しかし、問題なのが「同じ建物の近隣住民による騒音」です。
引っ越す前に大家さんや管理会社に「〇号室と〇号室と〇号室にはどんな方が住んでいますか?うるさくないですか?」などと確認することはできません。お試しで住んでみることも原則できないため、契約して引っ越して、実際暮らし始めて、それで初めて「ご近所さん」の騒音について知ることになるわけです。
マンションやアパートにおいて、騒音問題はつきものです。人間はどうしたって生活するのに音を立てます。無音で生活する人などいません。木造で壁や床が薄い建物だと、通常の足音や包丁を使う音なども漏れ聞こえることがあります。また、音楽やテレビを大音量で楽しみたい人や、友人を呼び騒ぎたい人、小さい子どもがいる家族などにおいては、かなり賑やかな音を発する頻度が高まります。
電話も気付かないうちに声が大きくなりがちなので、今回のケースで相談者様が気になったのも頷けます。まして、ベランダでの通話となると、相当うるさいことが容易に想像できます。
3.機関に相談した結果、「やみくもに裁判しない方がいい」という意見が多数

相談者様は消費者センターに相談して「裁判をしたらどうか」と言われたそうですが、アリネットでは弁護士やマンション管理士、都庁や宅建協会他の様々な窓口にも意見を求めてみました。その結果、やみくもに裁判しない方が賢い、つまり、掛けたコスト分の回収が難しいという意見が多数派だということが明らかになりました。
3-1.都庁の賃貸ホットラインの回答
都庁の賃貸ホットラインによる回答は「個人で裁判を起こすと金銭的のみならず、時間の経過と共に精神的ダメージも大きいのでやめた方がいい」というものでした。
対策としては、貸主に対して、隣人に音の問題を改善するよう言ってほしいと伝え、対応してもらうのが最善策だということでした。それでも改善しないならば、貸主から例の隣人に「迷惑行為の義務違反」として退去を促すという対応を取ってもらうのが良いそうです。
3-2.宅建協会の回答
宅建協会の回答も、都庁の賃貸ホットラインと同じく、「個人で裁判を起こすのはやめた方がいい」というものでした。
ただし、こちらは裁判を起こすならば、相談者自身ではなく、貸主が起こすのが良いということで、その上で強制退去させてもらい問題を解決するのはどうか、という提案でした。
3-3.アリネットとしての意見
アリネットとしても、賃貸ホットラインと宅建協会と全く同じで、個人で裁判を起こすのは非常に費用対効果が悪いと考えました。民事の簡易裁判をするのは簡単ですが、当然お金がかかりますし、賃貸ホットラインからの回答の通り、金銭面だけでなく精神的にも負担が大きいです。
裁判のために必要な調査をおこない(これにもお金がかかります)、裁判の日には仕事を休むなどの時間調整をし、相手が争う姿勢を見せた場合これに対抗し・・・と、かなり面倒です。これが大きなストレスとなるのは相談者様にとっても良くないことです。
そして、アリネットとしては1点気になったことがあったので相談者様に確認してみました。それは「実際の会話音の録音をしたり、騒音のデシベルを計測してみましたか?」ということでした。相談者様は「いえ、そこまでは・・・」と口ごもったので、過去の判例を見ても決定的な証拠が無い限りは裁判で争ってもほぼ勝ち目はない、とハッキリとお伝えしました。
とにかく、この手のご近所トラブルで裁判を起こすとなると、明らかに相手が悪い、明らかに相手が違反行為をしている、という証拠が無いと勝てません。騒音レベルを「見える化」するデシベル数を計測すると、環境庁や条例などで定められている数値を超えることがあります。しかし、その数値が出たからといって、「騒音で迷惑をかけている」という確固たる証拠にはならないのです。一時的に大きな音が出ることもありますし、今回のケースで言えば、「通話の音以外の音がうるさい」という可能性もあります。
ただ、いずれにせよデシベル数を計っておくことは交渉を進める上で非常に有益で、これを資料として貸主に提示することで注意を促しやすくなります(強制退去の勧告などもしやすくなります。)ちなみに、騒音の目安となるデシベル数は時間や地域によって異なりますが、ざっくり50~70デシベル以上と言われています。
ただ、よほどの異常事態でない限り、警察も弁護士もそれほど熱心には動いてくれないため、無駄骨となる可能性が高いと言わざるを得ません。そのため、アリネットとしても費用と時間を掛けてまで裁判を起こすのはお勧めできないのです。
ここで、相談者様にはひとつの判例をご紹介しました。騒音トラブルで裁判を起こしたものの、結局請求は棄却され、裁判費用なども全て原告(裁判を起こした側)の負担となってしまった残念なケースです。
4.騒音防止にと伴う判例紹介

以下、今回の相談者様に紹介した判例を共有します。
判例番号はL07531259で、2018年に起きた「騒音防止等請求事件」として記録されています。東京地方裁判所で2020年6月19日に判決が出ましたが、先述の通り、原告の請求は認められず、裁判費用なども全て自己負担となりました。
事件について簡単にまとめると、あるマンションに暮らす夫婦が、真上の家族の騒音について裁判を起こしたものの敗訴してしまったというものでした。
裁判を起こした夫婦も、真上に住む家族も、2014年ごろから当該マンションで暮らしはじめました。2015年1月ごろから、家族が住んでいる部屋から、子どもが走り回ったり飛んだり跳ねたりする音が、ほぼ毎日、早朝夜間を問わず断続的に3年もの間続いたとして、夫婦はこの家族を訴えることにしました。リビングやダイニング、寝室、玄関などで走る音や衝撃音があり、会話や睡眠にも影響が出て、心身ともに苦痛を被り平穏に生活する利益を侵害されたとして、この夫婦は慰謝料などを請求しました。
請求金額は家族全員に対して、慰謝料200万円、調査費用5万3784円、弁護士費用20万5378円、合計225万9162円でしたが、これらは全て棄却されました。
2018年5月26日から28日までの間にデシベル数を測定し、期間中には断続的に60デシベルや70デシベルを超える音が測定されました。しかし、測定したのが原告の部屋だったことから、この騒音の発信源が家族だけであるとは言い切れないということが棄却の理由となりました。
測定値は非常に細かく記録されて提出されましたが、逆に家族の主張として、家に不在だった時間帯や明らかに大きな音を立てていない時間帯も含まれてしまっていたため、不利になってしまった点も請求棄却の一因となりました。
4-1.騒音トラブルで裁判を起こして勝訴するのは相当難しい
この判例では、請求が棄却されて慰謝料を獲得できないばかりか、調査費用と弁護士費用で合わせて25万9162円を失ってしまうという、なんとも悲しい結果となりました。
このように、民事で裁判を起こしてもお金と時間を奪われ、ストレスだけが溜まり、結局慰謝料も取れない、という事態になる可能性が非常に高いのが現実です。
デシベル数を計測しても、それが明確な証拠して認められにくいため、このような結果となります。
5.相談者は貸主に再び被害を訴えることに
複数機関の回答やアリネットの意見、そしてアリネットが紹介した判例を知り、相談者様は個人的に裁判を起こすことを諦めました。そして、もう一度貸主と管理会社に騒音被害の現状を訴え、貸主自身から直接隣人に注意してもらうようお願いすることにしました。
それでも改善されないならば、貸主に強制退去の措置を取ってもらうなり、裁判を起こしてもらうなり、それなりの対処をしてもらうこともお願いしてみる、と仰っていました。
5-1.それでも改善されないようならば引っ越しを検討
ただ、貸主も人間ですし、強く言えなかったり、きちんと対応してくれなかったりする可能性があります。「貸主に相談しても一向に改善しない場合は引っ越してみてはいかがか」と提案してみると、相談者様も「そうですよね」と納得してくださいました。「負ける可能性が高い裁判で50万を失うぐらいなら、同じお金を引っ越し費用に充てた方がかしこいですよね。」
相談者様は、どこか吹っ切れたような表情でそう仰いました。私たち、アリネットとしても、この相談者様が平穏に幸せに暮らせることを心から願っていたので、引っ越しすることになった際に気を付けると良いポイントをお教えしました。この後、そのポイントをまとめますので、部屋探し中で騒音トラブルを避けたいという方は是非読んでみてください。
6.アリネットが提言する「騒音」トラブルを回避する3つのポイント

ご近所トラブルの代表格である騒音トラブルを事前に回避するためには、いくつかポイントがあります。ここでは、特に大切な3つのポイントをまとめました。
6-1.部屋探しではマンションやアパートの構造を確認
以前も建物の構造による騒音問題について、まとめましたが、マンションやアパートは大きく分けて、木造と鉄筋コンクリートの2種類に分類できます。木造の建物は非常に音漏れしやすく、古い建物の場合、通常の生活音ですら漏れ聞こえてしまうほどです。逆に、鉄筋コンクリートの建物、特に壁芯構造の建物は防音効果が高く、隣人の生活音が聞こえづらいのが特徴です。
騒音や他人の生活音が気になるという方は、木造よりも鉄筋コンクリートの建物、特に壁芯構造を選ぶと良いです。見分け方は建物の内見時に天井にある梁の大きさを確認したり、担当者に「この建物は壁芯構造の建物か」を確認してもらってください。この辺りは、将来あなたが損をしないためにとても大切だと思います。
>>壁芯構造など分かりづらい建物の構造と騒音に関する関係はこちらのページにまとめておきました。
6-2.角部屋や最上階を選ぶ
角部屋を選べば、「隣の部屋」は1つだけになります。また、最上階の部屋を選べば「上の部屋」が無いため、階上から聞こえてくる足音などが気になりません。最上階の角部屋を選べば、建物の中では最も「騒音被害が少ない部屋」に住むことができます。
>>家賃が高くても、騒音が少ない角部屋を選んだ方が良い理由について
>>上に人がいない最上階を選ぶメリット・デメリットについて
逆に、1階の部屋を選べば、「自分が立てる足音」を気にすることなく暮らせますので、騒音トラブルの加害者になりたくないという方にはおすすめです。
>>1階の部屋に関して、メリット・デメリットや住んでもいい1階について、こちらのページまとめました。部屋探しの参考にして下さい。
6-3.ファミリー層向けの物件を避ける
小さな子どもや赤ちゃんは、何かと賑やかなものです。「微笑ましい」と思えるぐらい心に余裕があれば良いのですが、これが「うるさいなぁ」となってしまうと大きなストレスとなります。
ファミリー層向けのマンションやアパートですと、どうしても子どもの数が増えます。逆に、一人暮らし用のワンルームが中心となっているマンションやアパートならば、ファミリーは少なく騒音被害の可能性も低くなります。
今回の相談者様は小さな子どもによる騒音ではなく、隣人の通話の音に悩んでいたため、一概にファミリー層を避けたからといって騒音問題も避けられるというわけではありません。ただ、騒音のリスクを抑えることはできますので参考にしてみてください。
7.もし、住み始めて騒音が気になったら、裁判費用よりも引っ越し費用をかけて快適な物件を探す

今回、これまでの経験を基に騒音リスクを下げる部屋探しのポイントを3つご紹介しましたが、実際に住んでみないと何とも分からないのが「隣人の騒音トラブル」の怖いところです。後から越してきた住人が騒音の発信源となることもありますし、いつ何時騒音に悩まされるか分かりません。
もし、隣人との騒音トラブルに悩んでいるのなら、先ずは過去の判例や自身の勝ち目について、よく調べ見て下さい。ご自身のケースでは、勝ち目がない、又は訴訟を行っても費用を回収できそうもない場合には、お金も時間も費やすよりも、残念ですがさっさと引っ越して環境を変えるのが良いと思います。ともかく、裁判費用にお金を使うのではなく、引っ越しにお金を使って、ストレスの元凶から離れてしまうことで快適な毎日を過ごすことができると思います。
自分にあった物件探しを進めるためにも、事故物件についてのスタンスとその調べ方や回避方法について、押さえておくのが大事です。念のため、建築士の方に内見時の確認点について、まとめてもらいました。役に立つと思うので、部屋探しの経験が2回以下の方は統計的に問題になるケースが多いので、ぜひ確認してみて下さい。
もし、住まいのトラブルで被害を訴えても管理会社や大家さんが動いてくれない場合、『住まいに関するトラブルに積極的に取り組んでいる不動産会社』、特に日常から建物の管理をしている会社への相談を検討してみてください。こういった不動産屋は数多くのトラブルを解決してきた経験や知識を保有しているため、あなたの満足のいく解決へと導いてくれます。
仮に、『住まいに関するトラブルに積極的に取り組んでいる不動産会社』に心当たりのない方は、アリネットの無料相談窓口からご相談ください。これまで8年間、300件以上のトラブルを弁護士や建築士等専門家と共に解決へと導いてきた実績と知識を保有しているため、あなたの力になることができると思います。ぜひ気軽にご相談ください。
部屋探しの経験が2回以下の方に特に、読んでほしい4,600件の失敗談を基に作った内見時のチェックリストはこちらのページです。人気のある他社の内見チェックリストも同様にまとめています。事故物件を調べ、見て来ましたが、実際に全てを網羅することはできません。そこで、建築士さんに住んでも良い事故物件の内見時の見分け方を教えてもらいました。念のため、確認し、内見に行ってみて下さい。他にも、今回同様、最近、お客様に聞かれた「内見の申し込み後のキャンセルって、罰金ありますか?」についてはこちらのページにまとめました。
私たちは、2012年より地域に根付いた不動産屋として、住まいのトラブルに特化し、住宅ローンの返済だけでなく、騒音や隣人、契約トラブル等のトラブルを解決してきました。
現在、無料相談を実施しており、相談者の方には住まいの問題解決事例をまとめた冊子も無料で差し上げております。問題を早期に解決し、一秒でも早く、明るい毎日を取り戻して下さい。ともかく、ぜひ一人で悩まず、時間を無駄にしない様、早めにご相談ください。
これまで、8年間300件近い住まいのトラブルの相談を受けた中でもさまざまなケースがありました。ただ、ここに記載出来ない内容で困っている方もいると思います。もし、あなたが現在トラブルに悩まされているのであれば、トラブルが大きくなる前にお近くの専門家に相談することをお勧めいたします。信頼できる先がすぐに見つからない場合、弊社の無料相談にご連絡ください。
これまで多くの住まいの問題を解決した経験や知識を活かし、あなたの力になれると思います。ぜひ気軽に無料相談までご連絡ください。私たちは今後もあなたの大切な人生と平穏が守られますよう、4,600件を超える引っ越しの失敗談を基に住まいの問題解決のトップランナーとして、専門家と協力し、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。
念のため、【建築士と考える】住んでもいい事故物件の見分け方、内覧時に使える方法をレクチャーしてもらいました。最近流行っているカスタマイズ賃貸についても、こちらにまとめました。不動産トラブル専門の弁護士による、契約直後の事故物件発覚時の告知義務違反等の対応についてはこちらのページにまとめました。
>>賃貸マンションの騒音問題を避けたい方向け、内見前の構造や間取り確認と引っ越し後の対策まとめ
>>マンションの内見後に入居申込をしたが、罰金無しでキャンセルはできますか?
今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

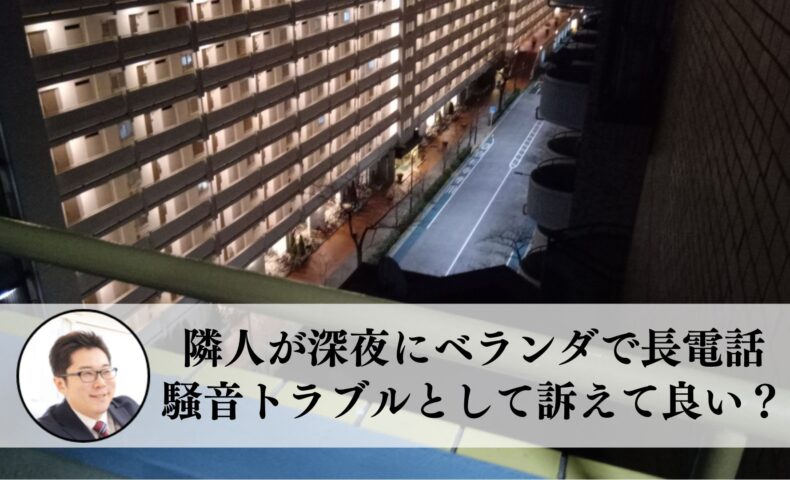




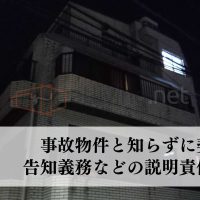
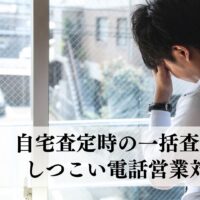






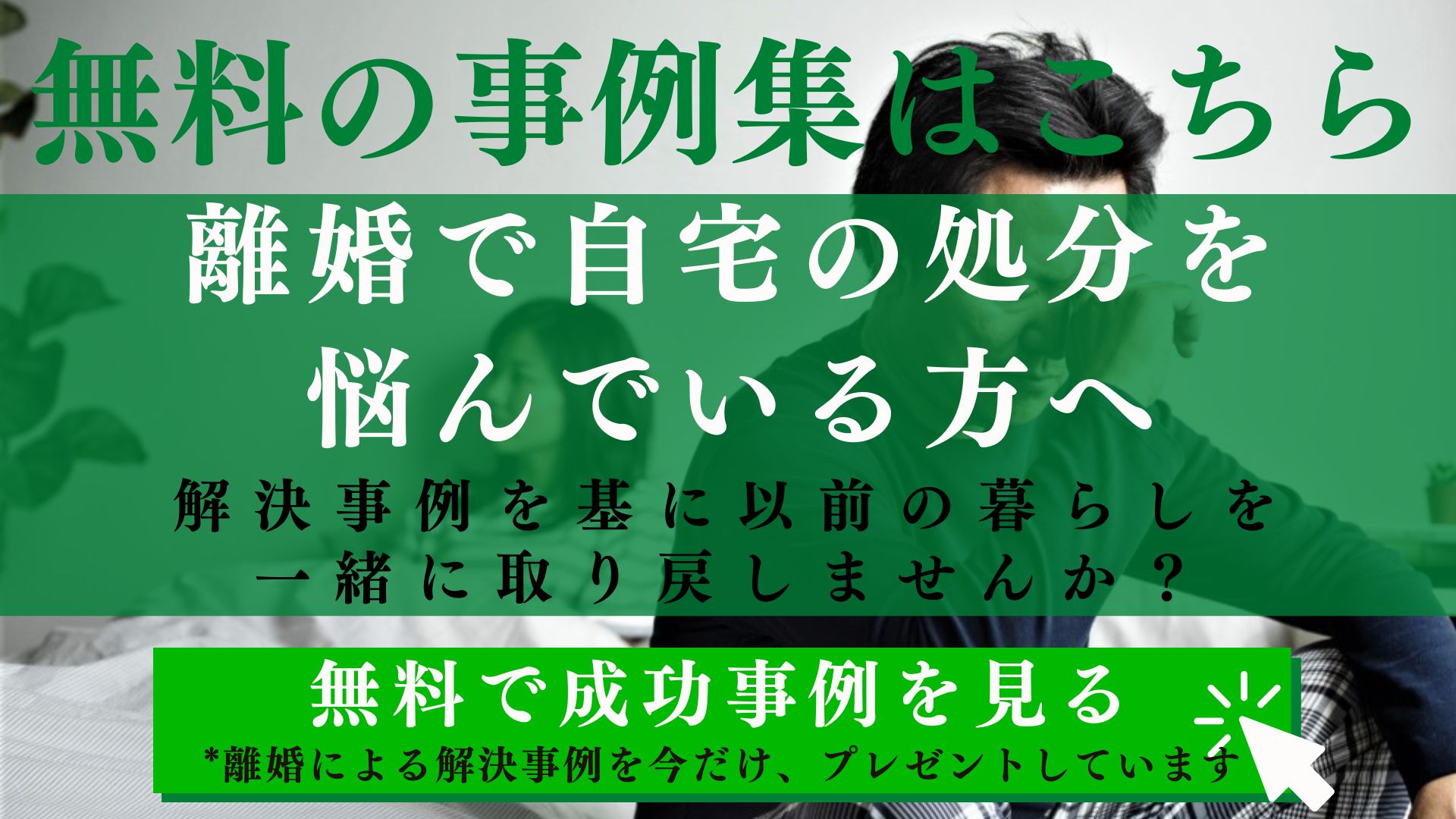
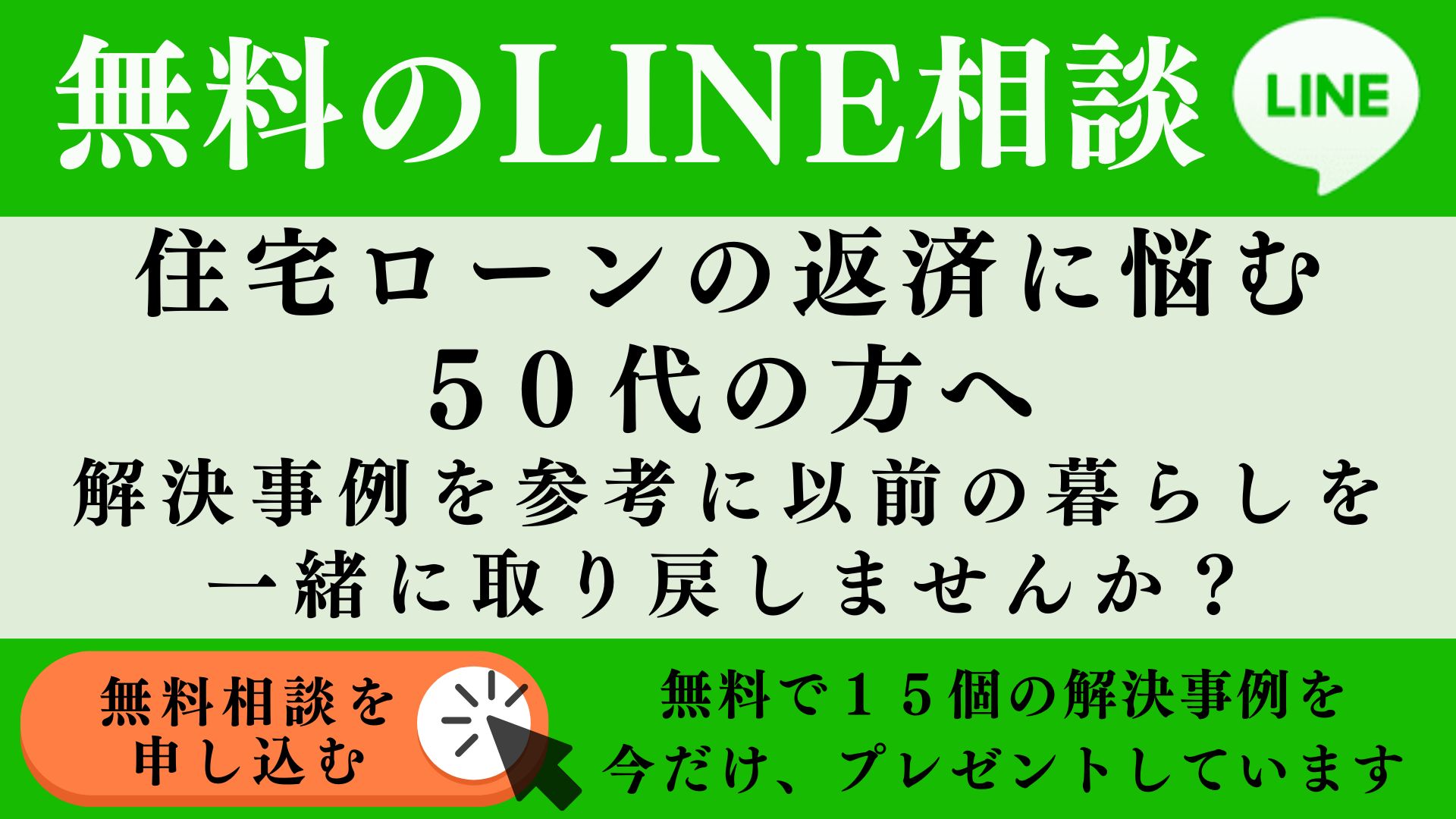
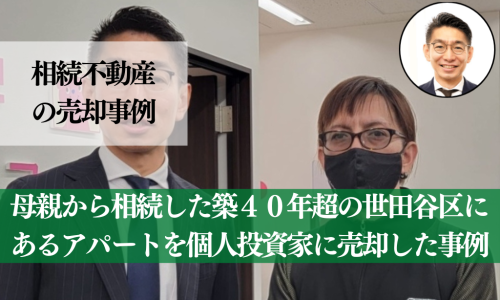
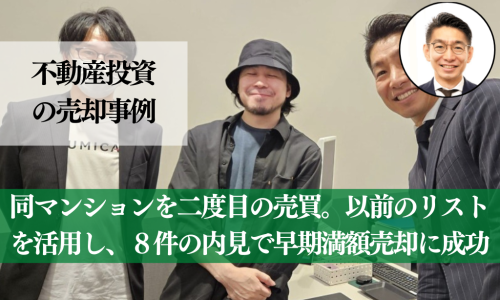
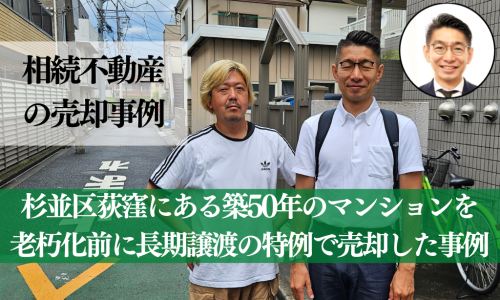

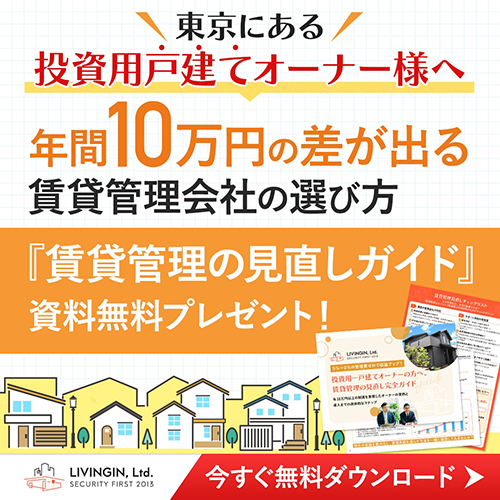
この記事へのコメントはありません。