離婚後も自宅に住み続けたい方へ、
こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

さまざまなメリットがあることから、離婚をしたあとでも、これまで住んでいた家に住み続けることを希望される方も多いです。
しかしそのためには、不動産の管理関係や財産分与をどのような形にするかなど、解決すべきことがあります。
そこで今回は、離婚後も家に住み続ける手続きはどのようにおこなえば良いか、住み続けることのメリット・デメリットについても解説します。
1.離婚で必要!住み続ける家の財産分与

まず、離婚する際の家の権利関係は、財産分与の考え方のもとに扱う必要があります。
1-1.離婚の際の財産分与とは?
財産分与とは、夫婦共同で築いた財産を離婚時に分配することを指します。
夫婦が共同で築いてきた財産は、寄与の割合はすべて均等とみなして、半分ずつ分けるのが原則となっています。
預貯金などを半分に分けるのは簡単ですが、不動産の場合均等に半分に分けるのは難しく、無理におこなえば価値が減ることがほとんどで、価値についても同意しにくいです。
そのため自宅については売却し、現金に換えた状態で財産分与をおこなうのが基本的な方法ですが、現状のままで分けて、どちらかが住み続けることも可能です。
そのためには、財産分与の方法を工夫する必要があります。
1-2.財産分与の方法
家を売却して財産分与するときは、売却額から譲渡所得税や住宅ローンの残債を差し引いた金額を分けます。
財産分与をおこなう際の贈与税は、高額の財産譲渡や贈与税逃れという判断がない限り課税されません。しかし、譲渡所得税に関しては控除や経費を差し引いた部分に対して課税されます。
一方、家を売却しないで元夫婦のどちらかの所有として住み続ける場合は、評価額の半分を住む方が住まない方へ現金または相当額の財産を渡すことで財産分与とします。
しかし、これはあくまで原則であり、財産分与の目的や財産分与全体の清算状況によって、分け方は臨機応変に変化します。
1-3.離婚後も家に住み続ける財産分与の考え方
財産分与には、以下の4種類の目的が設定されます。
- 清算的財産分与(夫婦の共有財産を分ける)
- 扶養的財産分与(離婚後の生活を維持する)
- 慰謝料的財産分与(慰謝料として支払う)
- 過去の婚姻費用の清算としての財産分与(生活費の未払いを清算する)
このように広範囲な目的のもと、例えば扶養的な意味合いにおいて、自宅を分けずに分与対象とすることもあります。
2.離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

そのまま住み続けることの、メリットとデメリットを整理していきます。
2-1.離婚後も家に住み続けるメリット
まず、夫婦の一方が大きく生活環境を変えることなく離婚後の暮らしを維持できる点は、大きなメリットと言えます。
子どもが転校する必要もないため、住環境が変化することなく、家族の心理的な負担を抑えられることになります。
住み続ける方は新しい住居での家賃の心配がなく、離婚時の話し合いの状況によっては、住宅ローンの返済も不要となります。
また、住み続ける場合は引っ越しに伴う費用や、準備の手間も必要がなくなります。
2-2.離婚後も家に住み続けるデメリット
離婚後もどちらかが住み続ける場合、デメリットの焦点は住宅ローンの支払いをめぐるトラブルのリスクです。
2-2-1.残債を一括で支払うリスク
まず、住んでいない方がローンを支払っていて返済が滞った場合、以下のようなことが考えられます。
ローンの支払い者が所在不明となった場合など、知らない間に滞納処理が進み、最悪競売となった時点で退去を迫られるというケースもあり得ます。
また、逆に自宅が共同名義のままで、家を出た方が連帯保証人を継続していた場合は、返済が滞ると連帯債務の支払い義務が生じて督促状が来る場合もあります。
つまり、以前住んでいた家の住宅ローンの残りを一括で支払うリスクを残すことになるのです。
2-2-2.所得制限額荷も注意が必要
また、妻子が元の家に住み、元夫がローンを支払っている場合、ローンの支払い分の金額は妻子の所得の一部とみなされます。
そのため、所得制限額を超えることで児童扶養手当(母子手当)が支給されない場合があります。
住宅ローンにまつわるトラブルを避けるための手続きについては、以降ご説明します。
3.離婚後も家に住み続けるための手続きとは?

離婚後も家に住み続ける方がいる場合に必要な手続きについて、ケースごとに解説します。
3-1.夫の支払いで夫が住み続けるケース
このケースでおこなう必要があるのは、連帯保証人の変更です。
前述のように、連帯保証人に妻が設定されているケースで、夫が住宅ローンを滞納した場合、妻が代わりに返済する必要が出てきます。
今は住んでいない、以前住んでいた家のローン返済を迫られることのないよう、妻が連帯保証人に設定されている場合には別の人に変更してもらう手続きをします。
返済能力がある夫の両親や、兄弟姉妹などを新しい連帯保証人として立て、変更しましょう。
新しい連帯保証人が見つからない場合は、住宅ローンの借り換えを打診します。しかし、夫婦共働きの収入を基準として借り入れし、残債が減っていない場合、借り換えは困難となることが多いです。
3-2.債務者が夫で妻が住み続けるケース
3-2-1.公正証書を作成する
このケースでは、金融機関に状況を説明したうえで、公正証書を作成しておくか、住宅ローンの名義変更をします。
金融機関への説明は、本来は住宅ローン契約違反である「住宅ローンの名義人が退去してローンを支払い続ける」ということに対して承諾を得るためです。
そのうえで、夫がローンを滞納した場合に備え、財産分与など離婚契約の取り決めを公正証書でおこなっておきます。
夫が財産分与の一環として住宅ローンを確実に支払い、滞納時には夫の財産から差し押さえなども可能にし、離婚後の暮らしを守るためです。
公正証書にしておけば、夫への財産開示請求がおこないやすくなり、夫が住宅ローンを滞納した場合でも財産の全体像を把握できます。
そうすることで、トラブルを未然に防ぐことができるため、夫婦双方が安心して過ごすことができます。
3-2-2.住宅ローンの名義変更をする
妻にローンの支払い能力がある場合、住宅ローンの名義を妻の名義に変更、もしくはローンを妻名義で借り替え、その分の財産分与は他の手段でおこなう方法もあります。
3-3.債務が夫婦共有名義で妻が住み続けるケース
このケースの対策でも、住宅ローンの借り換えをおこなうことが基本となります。
夫が住宅ローンを滞納した際のトラブルや、今後家を売却するなど各種の決定に夫の同意も必要となるなどの煩雑さを考えると、妻単独でのローン借り換えができれば、最も安心できます。
借り換えによってローンは妻の単独名義にして、夫は権利者から外しておきましょう。
金融機関は、どれくらいローンの返済残高があるのかと、妻の支払い能力があるかどうかの2つを主に審査しますが、まずは金融機関との相談をおこなうことを推奨します。
4.今回のまとめ

今回は、離婚後も家に住み続ける手続きはどのようにおこなえば良いのか、住み続けることのメリット・デメリットについても解説しました。
4-1.対策と話し合いが重要です。
離婚後のトラブルを未然に防ぎ、それぞれが安心して新しい生活を送るためには、必要な対策と、そのためにおこなう話し合いがカギとなります。
スムーズで理想に近い形で不動産売却をするためには、専門知識に基づいた検討のうえ、さまざまな手段の中から方針を決めて進めましょう。
4-2.離婚に伴うご自宅の売却で悩んでいる方へ

2012年以降、離婚に伴う100件近い相談を基に、離婚でローン破産しないためのチェックポイントをまとめました。
男の離婚問題で不動産の売却や買取りを検討している方、まずは簡単無料査定をお試しください。
- 夫婦の収入合算(連帯債務・連帯保証)等で自宅を購入
- ペアローンを含め、ローン総額が総収入の8倍以上
- 頭金なしのフルローンやオーバーローンで自宅を購入
- ローン金利は変動や当初固定で30年以上の長期で契約
- ボーナス払い年2回を使い、月々の返済を減らした
- 学費など毎月の生活費が高く、貯金が出来ない
- 借り入れの他、自宅の権利も夫婦で共有
- 夫婦間の会話が減り、子供と話す事が増えた
もし、2つ以上当てはまる場合には、専門家や私たちのLINE公式から離婚時の失敗診断をやってみて下さい。
どのような対策が取れるのか、その場でわかります。
特に、お仕事などで忙しい男性は言われるがままの方が多く、離婚問題で奥様との条件の書式化やご自宅の売却や買取りで悩んでいる方、簡単無料の『LINE公式の無料相談』や『電話相談』からお気軽にお問い合わせ下さい。
*私たちはたらい回しなく、実務担当が直接対応いたします。
スクリーンショット-410.png)
私たちは2012年以降、250件を超える、不動産取引を担当し、どのような不動産を購入・売却すべきか、理解しつつあります。
地方だけでなく、東京においても高齢化による住み替え相談が増えており、今後も私たちの強みを生かせる案件を丁寧に見つけ、紹介していきたいと思います。
>>これまでうまく行った解決事例はこちらのページにまとめてあります。
また、私たち、アリネットのgoogleでの口コミはこちらのページにまとめてあります

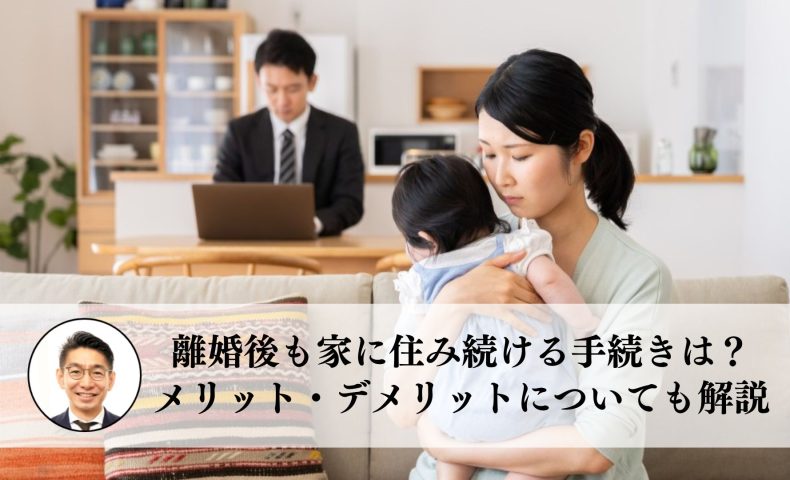




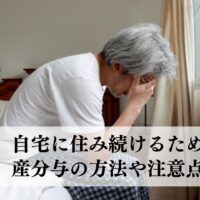




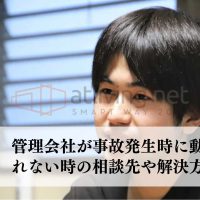


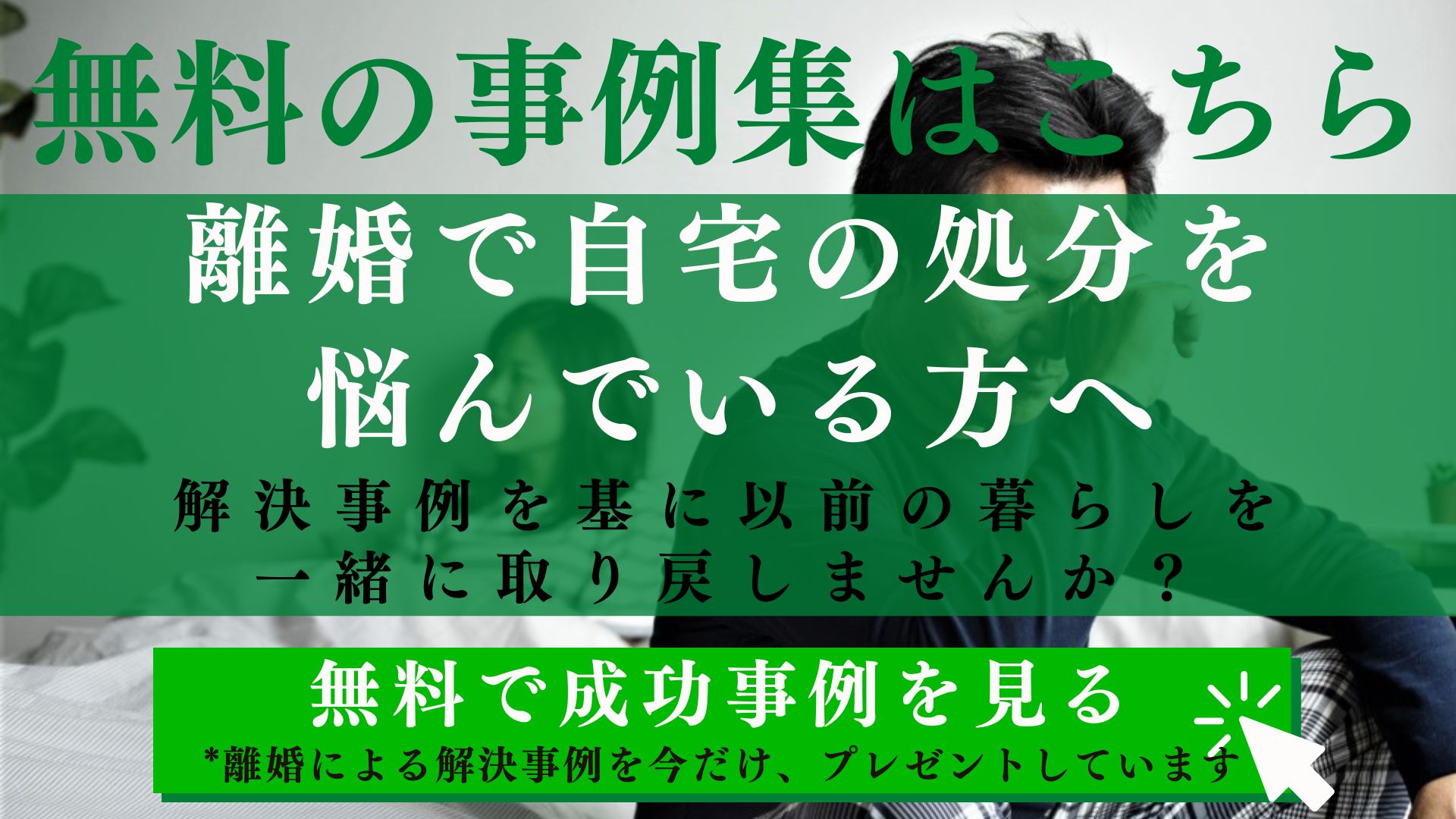
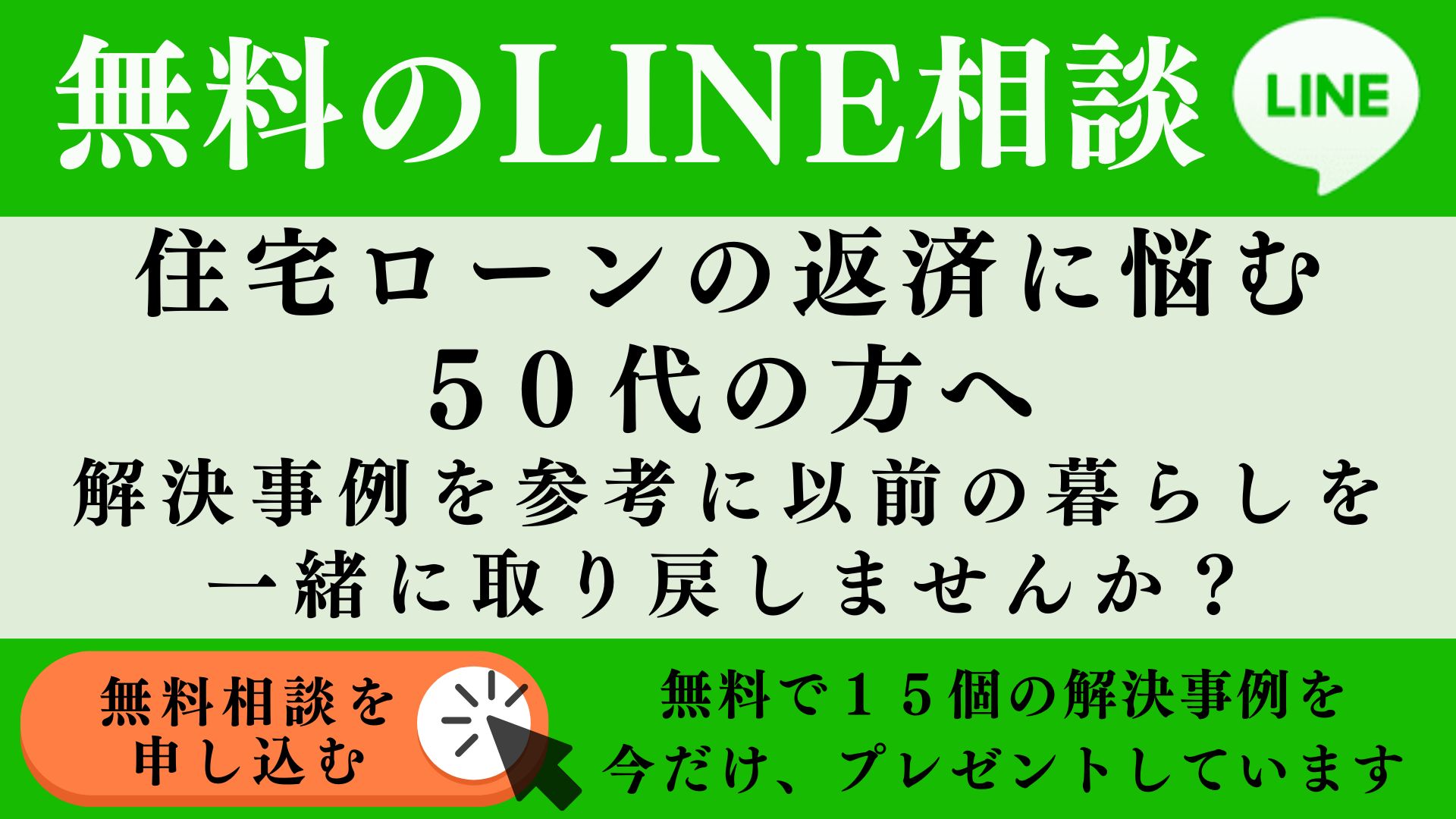
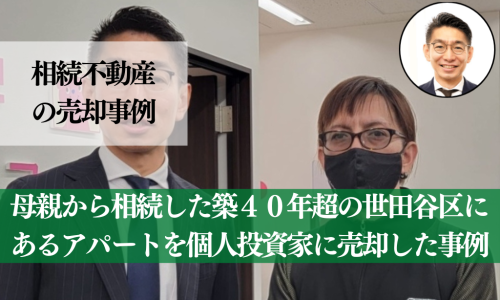
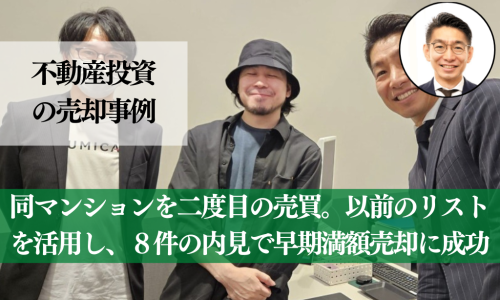
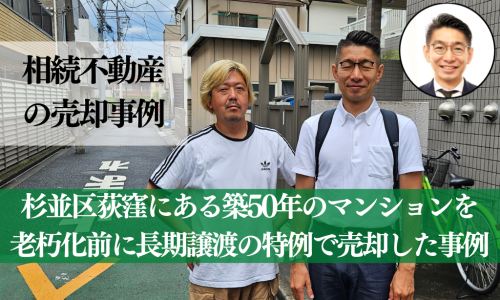

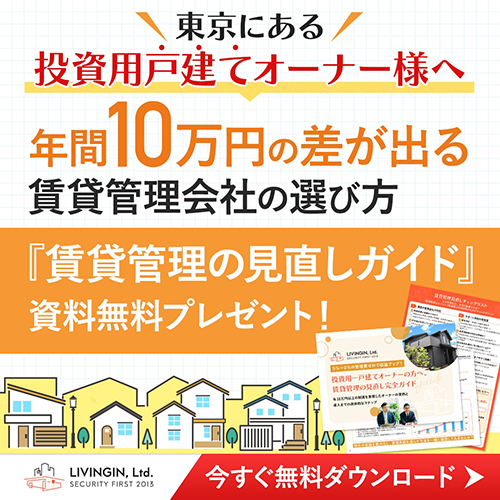
この記事へのコメントはありません。