目次

はじめに、相続した不動産を売却する場合、相続登記を行い名義を変更することが法律上必須となりました。
そのため、登記が済んでいない不動産は、相続人名義で売却することができず、売却手続きが進められない可能性があります。
そこで、今回は相続登記の重要性と、名義変更をスムーズに進めるための具体的な手続きについて詳しく解説します。
また、相続登記を行うタイミングや、売却の際に必要な書類や注意点など、基本的なことについても触れ、初めての方でも理解しやすいように解説していきます。。
1.相続登記とは?なぜ必要なのか?

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から相続人への不動産の名義変更手続きのことです。
相続登記は、相続人が不動産の所有者であることを公に主張するための重要な手続きであり、法律で定められた要件に基づいて申請する必要があります。
というのも、相続登記を行わないと、不動産の所有権が曖昧になり、様々なトラブルや不利益が生じる可能性があります。
特に、相続不動産を売却する際には、相続登記が必須です。
被相続人から直接買主への所有権移転登記はできないため、まずは相続人への名義変更が必要となります。
1-1.相続登記の基本的な役割
相続登記の主な役割は、相続人が不動産の所有者であることを公に主張することです。民法第177条により、登記がなければ第三者に対して権利を主張できないと定められています。
つまり、相続登記を行わないと、不動産は所有者不在の物件と同じで、他者に対して所有権を主張することができなくなってしまいます。
これは、不動産の売却や賃貸、担保設定をする際に大きな障害となります。
1-2.名義変更をしない場合のリスク
相続登記を放置し、名義変更をしないことには、以下のようなリスクがあります。
- 権利関係の複雑化:法定相続人の死亡により新たな相続人が発生し、権利関係が複雑化する可能性があります。
- 不動産売却の不可:登記を放置すると、被相続人名義のままで不動産を売却できません。
- 差し押さえのリスク:相続人が借金を抱えている場合、債権者による不動産の差し押さえが可能となります。
1-3.相続人が複数いる場合の対応
もし、相続人が複数いる場合、まず遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決定する必要があります。
法定相続分に基づく場合は協議書の提出は不要です。ただ、それ以外の場合は協議書が必要となります。
もし、遺産分割協議が難航する場合は、相続人申告登記を利用することで義務を一時的に免れることができます。
ただし、これはあくまで一時的な措置であり、最終的には相続登記を完了させる必要があります。
相続人が複数いる場合、円滑に相続登記を進めるためには、早めに司法書士などの専門家に相談し、適切な手順を踏むことが重要です。
弁護士や司法書士、不動産の専門家などに相談することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。
2.相続登記と名義変更の手続きの流れ
相続登記と名義変更は、相続不動産を売却する際に欠かせない手続きです。
ここからは、相続登記の手続きを始めるタイミングや必要な書類、登記申請の流れについて詳しく解説します。
また、名義変更をスムーズに進めるためのコツについても触れていきます。
2-1.相続登記の手続きを始めるタイミング
相続登記の手続きは、被相続人の死亡後、できるだけ早いタイミングで開始することが重要です。
2024年4月1日より相続登記が義務化されたため、登記申請の期限を過ぎると罰則があります。
また、繰り返しにはなりますが、相続登記を放置することで様々なリスクも出てきます。
こうしたトラブルを避けるためにも、相続登記は早めに着手することをおすすめします。
(内容の重複が多いため、再考をお願いします)
2-2.必要な書類と登記申請の流れ
相続登記を申請する際には、様々な書類を準備する必要があります。
まず、登記申請書や遺産分割協議書、相続関係説明書(戸籍・除籍謄本の原本還付希望の場合)、委任状(代理人に依頼する場合)などを作成します。
また、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)や住民票の除票、相続人の戸籍謄本(死亡日以降に発行)、相続人の印鑑証明書、固定資産評価証明書(登記申請日に属する年度のもの)なども集める必要があります。
これらの書類を揃えたら、法務局に登記申請書を提出し、審査を受けます。もし、必要書類に不備がなければ、申請から1週間程度で相続登記がだいたい完了します。
一般的には、登記完了のタイミングで不動産会社に売却手続きを依頼し、媒介契約を締結します。
その後、買主が見つかれば手付金を受け取り、売買契約を締結、決済後に所有権移転登記の申請と不動産の引き渡しを行います。
2-3.名義変更をスムーズに進めるためのコツ
相続登記と名義変更をスムーズに進めるためには、いくつかのコツがあります。
まず、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを明確に決定しておくことが重要です。
次に、法定相続分に基づく場合は、協議書の提出は不要です。ただ、相続人間で合意形成を図ることで後のトラブルを防ぐことができます。
また、相続登記の申請に必要な書類を早めに準備しておくことも大切です。
特に、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本などは、取得に時間がかかる場合があります。
そのため、書類の収集は計画的に行い、余裕を持って申請をしてください。
以上のような点に留意しながら、相続登記と名義変更の手続きを進めていくことが、相続不動産の売却を成功させるカギになります。
3.相続登記が未了でも売却できるケースとそのリスク

相続登記が未了の場合でも、一定の条件を満たせば不動産を売却することは可能です。
しかし、そのためには相続人全員の同意が必要不可欠であり、また、買主側のリスクも高まるため、売却価格が下がる可能性があります。
ここから、相続登記が済んでいない不動産を売却する際の制約や、名義変更が必要な理由とそのリスク管理について解説します。
3-1.登記が済んでいない不動産の売却の制約
相続登記が未了の不動産を売却する場合、以下のような制約があります。
- 相続人全員の同意が必要登記名義人が死亡している場合、相続人全員の同意がなければ売却できません。一人でも反対する相続人がいれば、売却は困難になります。
- 買主のリスクが高まる登記名義人が存命でない不動産は、買主にとってリスクが高い物件と見なされます。将来的に相続人間で紛争が発生し、売買契約が無効になる可能性があるからです。
- 売却価格が下がる可能性買主が負うリスクが高いため、売却価格は相場より低くなる傾向にあります。円滑な取引のためには、価格面での譲歩が必要になります。
3-2.名義変更が必要な理由とリスク管理
相続登記による名義変更が必要な理由は、以下の3点です。
- 所有権の明確化登記は所有権を公示するための手段です。相続登記を行わない限り、(指定マーカー)不動産の所有者が誰なのか、法的に明らかになりません。
- 第三者対抗要件の具備民法177条により、登記をしなければ第三者に対して所有権を主張できません。つまり、登記なき不動産は、法的に無主物となってしまいます。
- トラブル防止相続登記が未了だと、相続人の一部が知らないうちに勝手に売却されるなど、トラブルに巻き込まれるリスクがあります。こうしたリスクを管理するには、速やかな名義変更が不可欠です。
3-3.名義変更を省略して売却することは可能か?
原則として、名義変更を省略して相続不動産を売却することはできません。相続人全員の同意と、相続登記による名義変更が必須であるためです。
ただし、売主の事情によっては名義変更を一時的に保留する方法として、前述の章で触れた「相続人申告登記」を活用する手法があります。
この方法は、遺産分割が確定するまでの間、暫定的に相続人全員を登記名義人とする手続きです。ただし、
相続人申告登記はあくまで暫定的な措置に過ぎません。最終的には適切な名義変更手続きを行う必要があります。
4.相続登記の費用と必要な期間
相続登記の手続きを進める上で、費用と期間について知っておいてほしいです。
登記にかかる費用の内訳や手続きにかかる時間の見通しを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
また、司法書士や専門家に依頼する場合の費用についても、事前に把握しておくことが重要です。
ここでは、相続登記の費用と必要な期間について詳しく解説していきます。
4-1.登記手続きにかかる費用の内訳
相続登記の手続きにかかる費用は、主に以下の項目から構成されています。
- 登録免許税
- 郵送料
- 戸籍謄本や住民票などの取得費用
- 司法書士への報酬(依頼する場合)
登録免許税は、不動産の価格に応じて変動します。例えば、価格が1,000万円以下の場合は0.4%、1,000万円を超える場合は0.4%+2万円となります。
また、郵送料や戸籍謄本等の取得費用は、数千円程度が一般的です。
司法書士に依頼する場合は、報酬が別途必要になります。
報酬は物件の複雑さや、司法書士事務所ごとに異なるため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。
4-2.手続きにかかる時間の見通し
相続登記の手続きにかかる時間は、ケースによって大きく異なります。一般的には、必要書類を揃えてから登記完了まで、1~2ヶ月程度が目安とされています。
ただし、相続人の確定や遺産分割協議に時間がかかる場合、手続き全体の期間が長引く可能性があります。また、書類の不備や修正が必要な場合も、完了までの時間が延びる要因となります。
そのため、手続きをスムーズに進めるためには、必要書類を事前に準備し、相続人全員の合意形成を図ることが大切です。
4-3.司法書士や専門家に依頼する際の費用
相続登記の手続きは、専門的な知識が必要とされるため、司法書士などの専門家に依頼するケースが多いです。
司法書士への報酬は、物件の価格や相続人の数、申請方法などによって異なります。
一般的な目安としては、以下のような金額が相場とされています。
| 物件価格 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 15万円~20万円 |
| 1,000万円~3,000万円 | 20万円~30万円 |
| 3,000万円~5,000万円 | 30万円~40万円 |
ただし、遺産分割協議が複雑な場合や、相続人が多数いる場合は、さらに費用が高くなる傾向にあります。
依頼する際は、複数の司法書士事務所から見積もりを取り、費用とサービスの内容を比較検討することが重要です。
5.名義変更後に不動産を売却する際の注意点
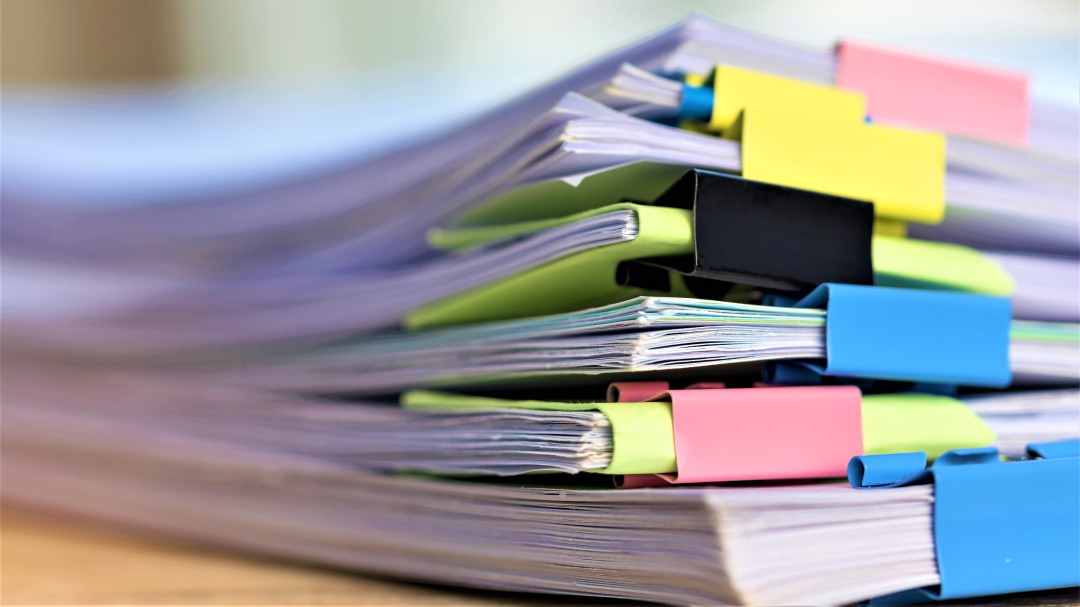
相続登記を行い、不動産の名義変更が完了した後、売却を検討する場合には、いくつか注意点があります。
ここでは、売却時に確認すべき書類、税金との関連性、そして相続財産の分配方法について詳しく解説していきます。
5-1.不動産売却時に確認すべき書類
名義変更後に不動産を売却する際は、以下の書類を確認することが大切です。
- 登記簿謄本: 不動産の所有者や権利関係を確認できる公的な書類です。
- 固定資産評価証明書: 不動産の評価額を確認できる書類で、税金計算の基礎となります。
- 建物図面: 建物の間取りや面積を確認できる書類です。
- 建築確認済証: 建物が建築基準法に適合していることを証明する書類です。
これらの書類を事前に準備しておくことで、スムーズに売却手続きができます。
また、買主側からの要求にも迅速に対応できるようになります。
5-2.売却にかかる税金と名義変更との関連
不動産売却時には、譲渡所得税や住民税などの税金が発生します。
これらの税金は、名義変更の時期によって異なる場合があります。
| 名義変更の時期 | 税金の計算方法 |
|---|---|
| 売却前に名義変更 | 相続人の取得価格を基に計算 |
| 売却後に名義変更 | 被相続人の取得価格を基に計算 |
売却前に名義変更を行った場合、相続人の取得価格を基に税金が計算されるため、税負担が軽減される可能性があります。
一方、売却後に名義変更を行うと、被相続人の取得価格を基に税金が計算されるため、税負担が増える可能性があります。
5-3.売却後の相続財産の分配方法
不動産を売却した後、得られた売却代金は相続財産として扱われます。
この売却代金を相続人間で分配する際には、以下の点に注意が必要です。
- 遺産分割協議: 相続人全員で話し合い、分配方法を決定します。
- 法定相続分: 遺言がない場合、民法で定められた法定相続分に基づいて分配します。
- 遺言の有無: 遺言がある場合は、その内容に従って分配を行います。
売却代金の分配方法については、相続人間で事前に合意しておくことが重要です。
合意がない場合、紛争に発展する可能性があります。
そのため、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
6.専門家のサポートを受けてスムーズに進める方法
相続登記や不動産売却の手続きは複雑で、専門的な知識が必要とされます。しかし、一人で全てを把握し、進めていくのは容易ではありません。
そこで、司法書士や不動産会社などの専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
6-1.司法書士や不動産会社の役割
司法書士は、相続登記の申請や各種書類の作成を代行してくれる法律の専門家です。
相続人の確定から遺産分割協議、登記申請までの一連の手続きをサポートしてくれます。
一方、不動産会社は、相続不動産の売却に特化したサービスを提供しています。
物件の査定、広告、買主とのマッチング、契約締結までを担当し、売却価格の最大化を目指します。
6-2.相続登記を司法書士に依頼するメリット
ここまで説明してきましたが、相続登記を自分で行うには、多くの時間と労力が必要です。
また、書類の不備や手続きの誤りがあると、登記が完了せず、売却に支障をきたす可能性もあります。
そのような手続きを司法書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 相続人調査や遺産分割協議の支援により、手続きがスムーズに進む
- 必要書類の作成や提出を代行してくれるため、時間と手間が省ける
- 専門的な知識により、登記申請の誤りや遅延を防げる
6-3.専門家との連携でトラブルを避ける
相続不動産の売却では、権利関係の複雑さや物件の状態など、様々な問題が発生する可能性があります。
司法書士と不動産会社が連携することでこれらのトラブルを未然に防ぐことができます。
例えば、過去の成功事例を見てみると、千葉県松戸市の中古戸建売却では、不動産会社が売却条件を明確にし、適切な購入者を見つけることで、スムーズな取引が実現しました。
また、相続したマンションの売却事例では、小修繕や掃除により物件の魅力を引き出し、需要の高い層にアプローチすることで、高値での売却に成功しています。
このように、専門家との連携により、相続登記から不動産売却までの一連の手続きを円滑に進めることができます。
7.名義変更の重要性と手続きまとめ

ここまで解説してきたように、相続不動産の売却を検討する際、相続登記による名義変更は必要不可欠です。
また、相続登記を行わずに売却しようとすると、様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
さらに、2024年4月から相続登記が義務化されたため、期限内に手続きを完了させる必要もあります。
そこで、司法書士や不動産会社と連携することで、相続登記から売却までの一連の手続きを円滑に進めることができます。
相続不動産の売却を検討している方は、是非今回の記事を参考にしていただき、ご自身の売却活動に活かしてください
もし、不動産の売却に関する疑問や不安がある方は、『無料の相続不動産売却事例勉強会』への参加をおすすめします。
ご両親から引き継いだ大切な実家などの売却のノウハウを学べるだけでなく、実際に売却の実務を行っている専門家からの具体的なアドバイスも受けられる貴重な機会です。
参加者は実際に老朽化した空き家をお持ちで、あなたと同じような不安を感じていらっしゃいます。
ぜひ、勉強会で得た知識を糧に、空き家の高値売却への一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
参考文献
https://www.cruise-company.co.jp/column/inheritance

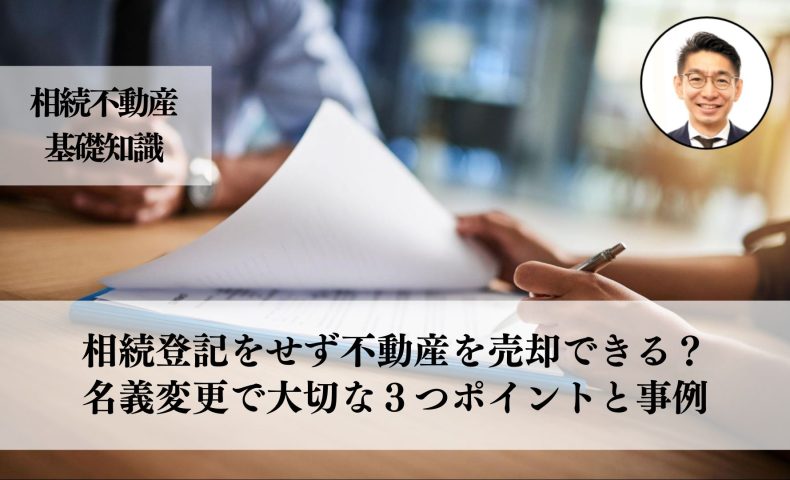


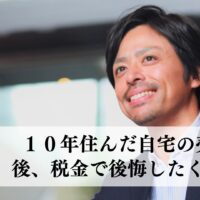

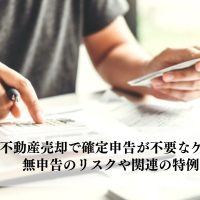







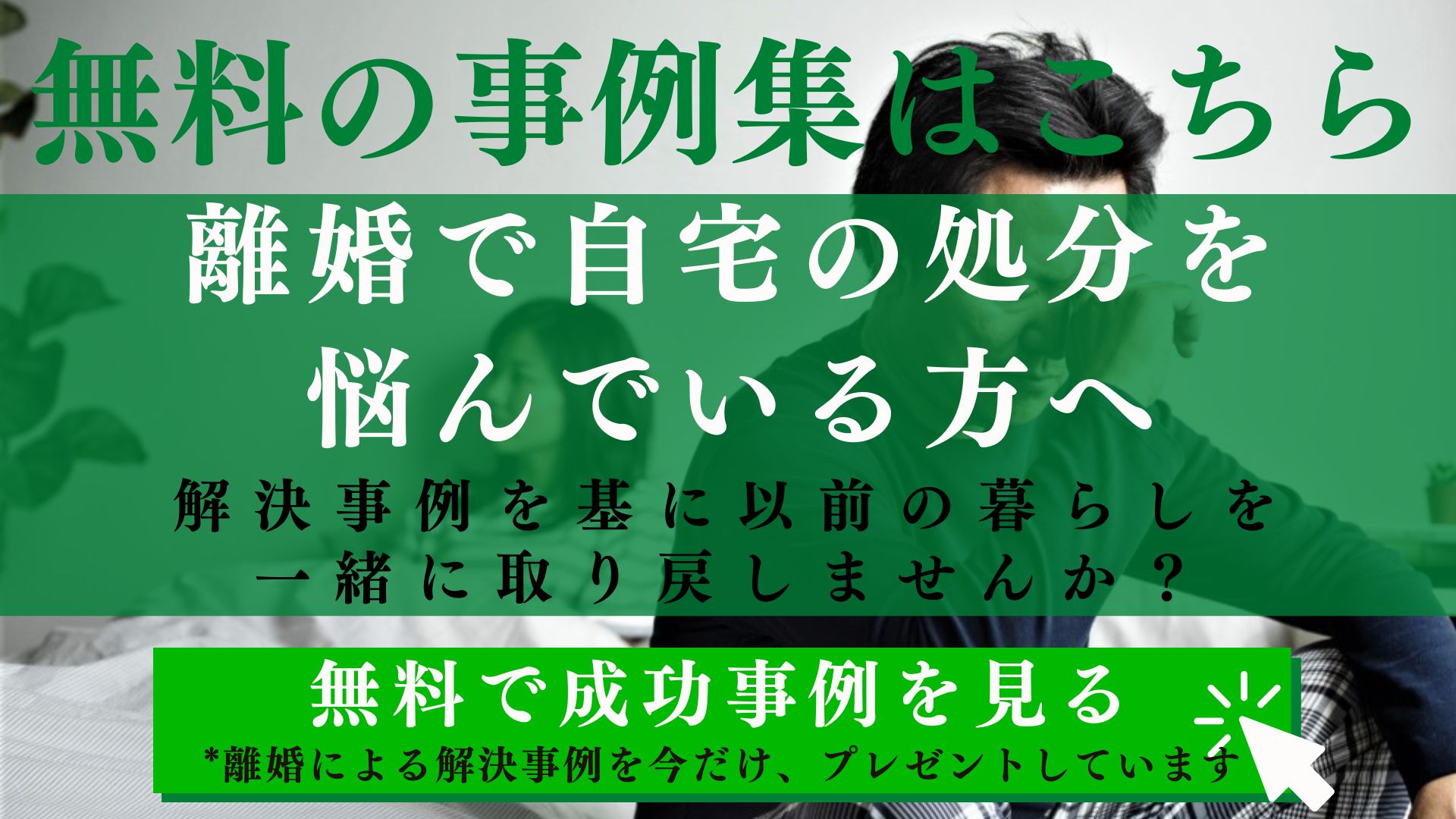
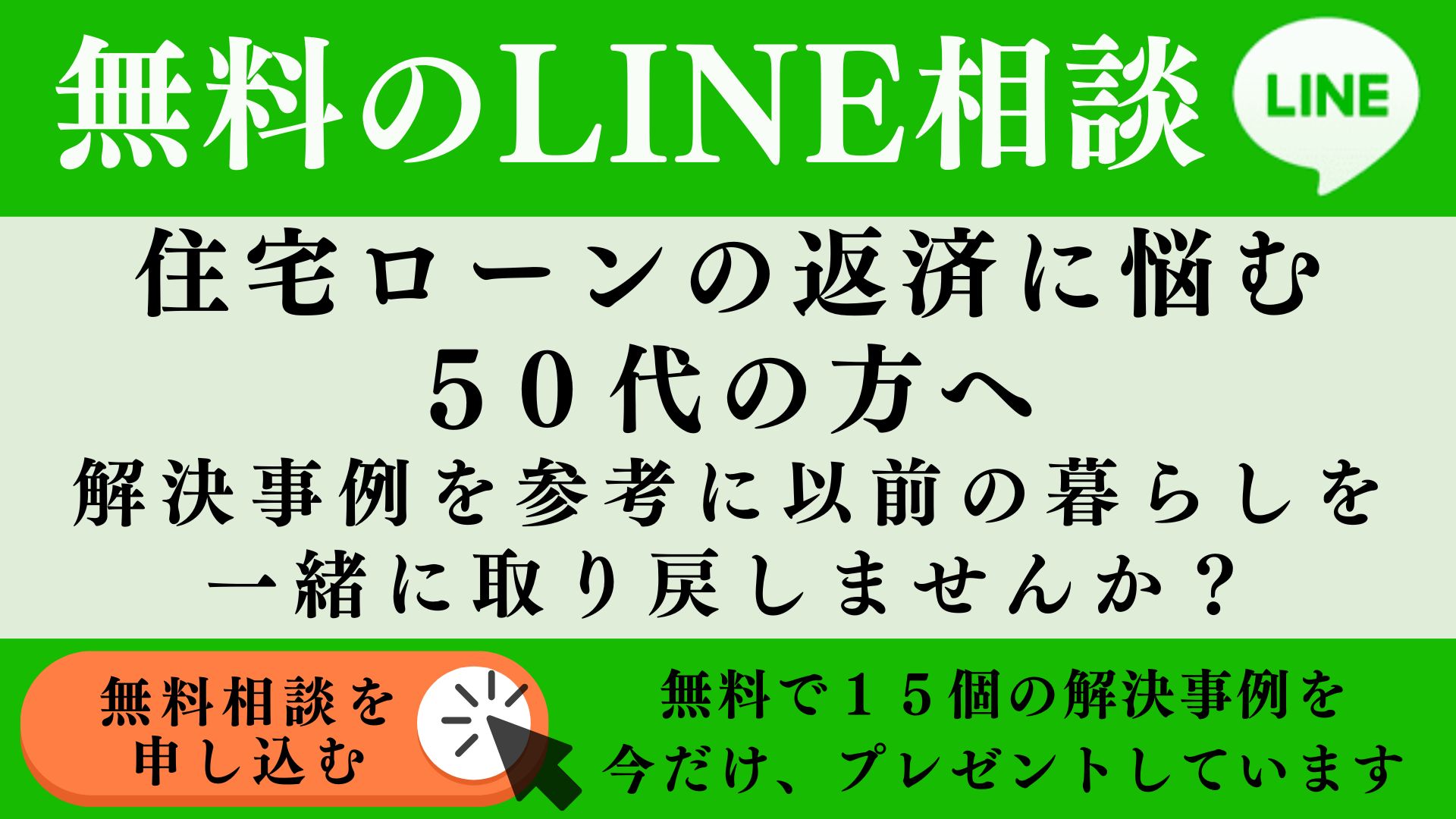
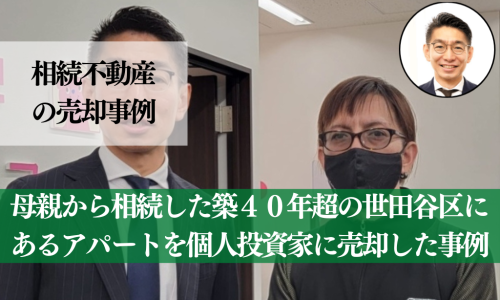
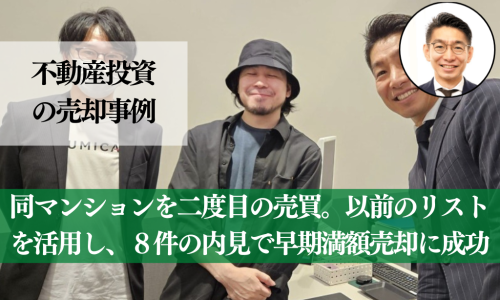
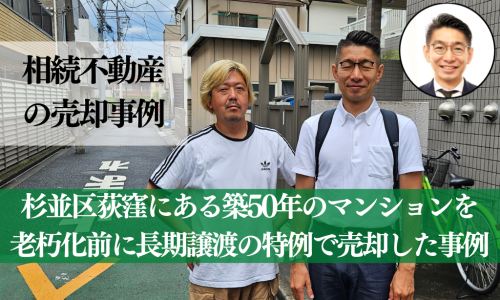

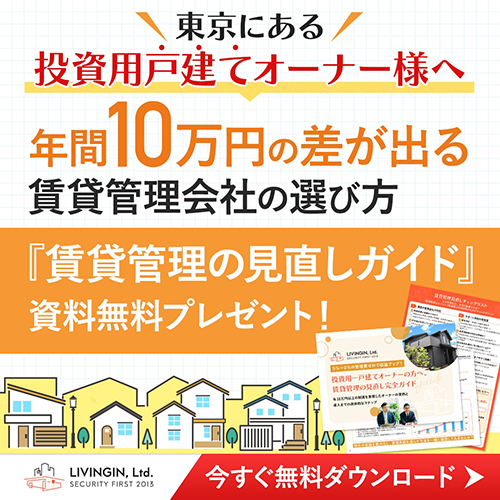
この記事へのコメントはありません。