今回は、進学や就職でこの時期に増えるシェアルームや両親による代理契約に関して、その違法性や入居者として注意すべき点に関して、元弁護士の福谷さんと一緒にその辺り、考えました。以下、それぞれ個別に見ていきます。
賃貸住宅を借りるとき、本人が忙しい場合や高齢で物事を判断しにくくなっている場合など、他人が「代理」で進められると便利です。また、ルームシェアを契約するときには、代表者が1人で契約するのか、全員が契約者になるのか、それぞれの場合について、法律的に正しい方法を理解しておきましょう。
今回も不動産専門の元弁護士の福谷さんと「代理人」による契約方法と「ルームシェア」の契約方法を解説します。
1.法定代理人と任意代理人

不動産を借りるとき、本人の代わりに代理人を立てて契約手続きを進めることは法律的に可能です。たとえば、本人が忙しいときや高齢者で判断能力が低いときなどに代理人を立てるケースが多数です。
代理人には「法定代理人」と「任意代理人」があります。法定代理人は「法律上当然に代理人になる人」、任意代理人は「本人が選ぶ代理人」です。法定代理人がつくケースは、法律によって限定されています。法定代理人のいるケースでは本人が単独で契約できず、法定代理人が同意するか、代理して契約手続きを進める必要があります。
一方、法定代理人のいない人は基本的に自分で契約する必要があります。他人に頼みたければ、任意代理人を選任しなければなりません。
2.法定代理人の種類

法定代理人には、以下のような種類があります。
2-1.親権者
未成年の場合、両親が基本的に「親権者」として法定代理人になります。ただし、離婚後子どもの親権者にならなかった方の親には親権が認められず、親権者と指定された一方の親のみが代理権を持ちます。たとえば、未成年者が賃貸住宅を借りる際には、親が代理で契約する必要があります。
2-2.未成年後見人
親のいない未成年の場合、未成年後見人が法定代理人となります。賃貸借契約をするときには家庭裁判所に申立をして「未成年後見人」をつけた上で、後見人によって契約を進める必要があります。
2-3.成年後見人
高齢になり、判断能力の低下した高齢者などの場合、成年後見人が法定代理人となります。家庭裁判所で「成年後見人」を選任した上で、後見人によって不動産賃貸借契約を締結する必要があります。
たとえば、親が重度の認知症にかかっている場合などには、親本人に契約をさせると無効になってしまうおそれがあるので、必ず家庭裁判所で成年後見人を選任した上で契約手続きを進めましょう。
3.任意代理人の選任方法

法定代理人がつかない方が人に代理で契約させるには「委任状」が必要です。委任状は「この人に不動産の賃貸契約を任せます」ということを証明するための書類です。ただ、委任状は悪用されやすいので取扱いに注意が必要です。
その為、必ず「委任先の人」や「委任内容」を明らかにしましょう。たとえば「〇〇の物件を家賃〇〇円で賃借する件について、〇〇〇〇氏に委任する」などと書きます。間違っても委任事項を白紙にした「白紙委任状」を渡してはなりません。
また、代理人には実印や印鑑登録証明書、身分証明書のコピーなどの重要書類を預けなければならないので、信用できる人にしか代理を依頼してはなりません。親や兄弟などの親族か弁護士・司法書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。
4.シェアルームの契約方法

次に、就職や進学が多いこの時期に増える友達や兄弟・姉妹、同棲等の「シェアルーム」の契約方法をみていきましょう。
シェアルームの契約方法には2通りがあります。1つは「複数の人でルームシェア(同居)」する場合、もう1つは「1つの物件を知らない人と居住スペースを分けてシェアする(シェアハウス)」場合です。どちらに該当するかで契約方法が異なります。
5.「ルームシェア」のケース

5-1.基本的な契約方法
友人3人が一緒に住むことにしたなど「ルームシェア」の場合、以下の2つの契約方法から選択できます。
・代表者1人が契約者となって契約書を作成する
・全員が連名で契約する
代表者1人が契約者になると、契約手続きは簡単ですが、代表者1人に責任が集中してしまいトラブルにつながるおそれが高まります。たとえば、法的な家賃の支払い義務は代表者に発生するので、他の人が支払いをしなかったときにも代表者へ督促がきてしまいます。また、連帯保証人は「代表者の親族」を差し入れるよう求められるケースが多いので、他の入居者がトラブルを起こしたときにも、代表者の親族に迷惑が及ぶ可能性があります。
一方、全員の連名契約にした場合、家賃は全員が負担しますし、連帯保証人も1人1人について設定するので、特定の入居者のみの負担が重くなりすぎるのを避けられます。個人的に、契約人数が増えるので手間が増えますが、おすすめはコチラです。ただ、誰か一人だけが退去する場合、以下のように面倒な手間が発生します。
5-2.退去する場合
ルームシェアの場合でも、同居人のうち1人が退去するときには必ず大家に告げる必要があります。連名契約なら契約者が変わってしまうので、契約書の作り直しや確認書の作成が必要となる可能性もあります。代表者1人が契約している場合、代表者以外の人が退去するなら契約者の変更は不要ですが、代表者が退去するなら、契約名義を変更して契約書を作り直す必要があります。
6.「ルームシェア」に個別入居するケース

6-1.基本的な契約方法
1つのシェアハウスの中に、全然知らない他人同士が暮らしている場合などでは、1人1人の入居者が個別に大家と賃貸借契約を締結する必要があります。家賃も1人1人について設定され、滞納したら滞納した本人に請求されます。他の契約者の滞納料金を別の入居者が支払う必要はありません。連帯保証人も1人1人の入居者について設定されるので、他の人が家賃を払わなかったために別の人の親族に迷惑が及ぶ可能性はありません。
6-2.退去する場合
1人が退去する場合、その1人と大家が話し合って契約を終了させれば良いだけで、他の賃借人には影響しません。
7.代理、連名契約のまとめ

マンションやお部屋を借りる時、人に契約の代理人を依頼したり、代表者となって契約したりすると、手間とリスクが発生します。正しい方法を知って、安全に手続きを進めていきましょう。
今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して、結果と原因のみ、記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。
【元弁護士と考える】シリーズ、告知義務の必要な事故物件を選ばないための賢い対策他
>>【元弁護士と考える】事故物件を契約する前の告知義務?その確認方法や注意点は?
>>【元弁護士と考える】賃貸契約後に『事故物件』と判明、解約や損害賠償できます?
>>【元弁護士と考える】不動産屋からウソを教えられた時の対応は?
>>【元弁護士と考える】騒音、地震、虫などないと言われたのに、嘘だったら
>>【元弁護士と考える】騒音や悪臭、ナンパ等『隣人トラブル』の対処と引っ越し代は?
その他、事故物件に関する記事はこちらです。
>>麻布十番の事故物件を見に行って、その場で原因分析(その1)
>>麻布十番の事故物件を見に行って、その場で原因分析(その2)
今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。










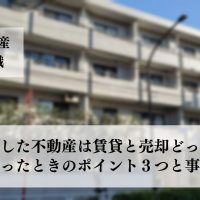



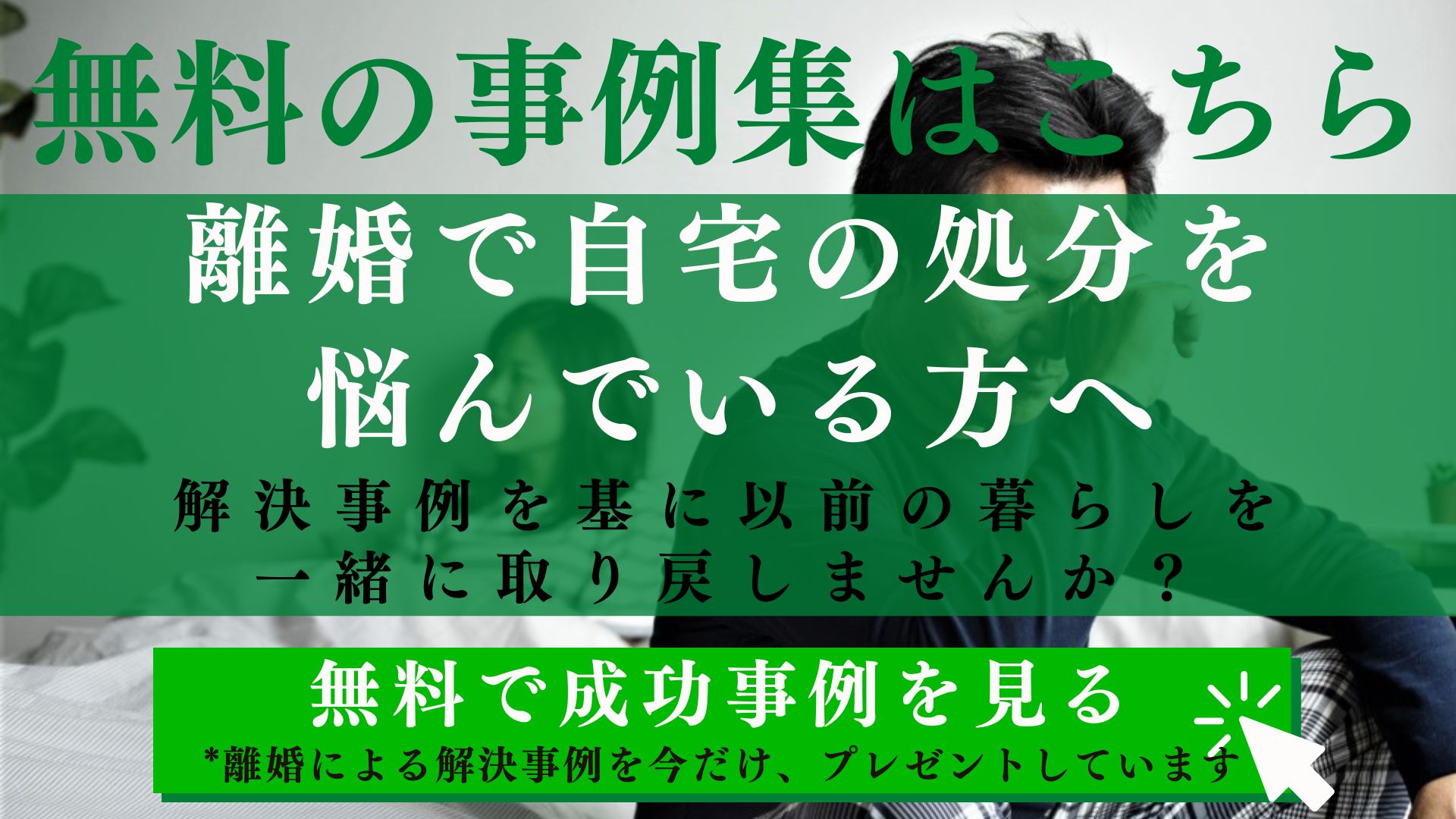
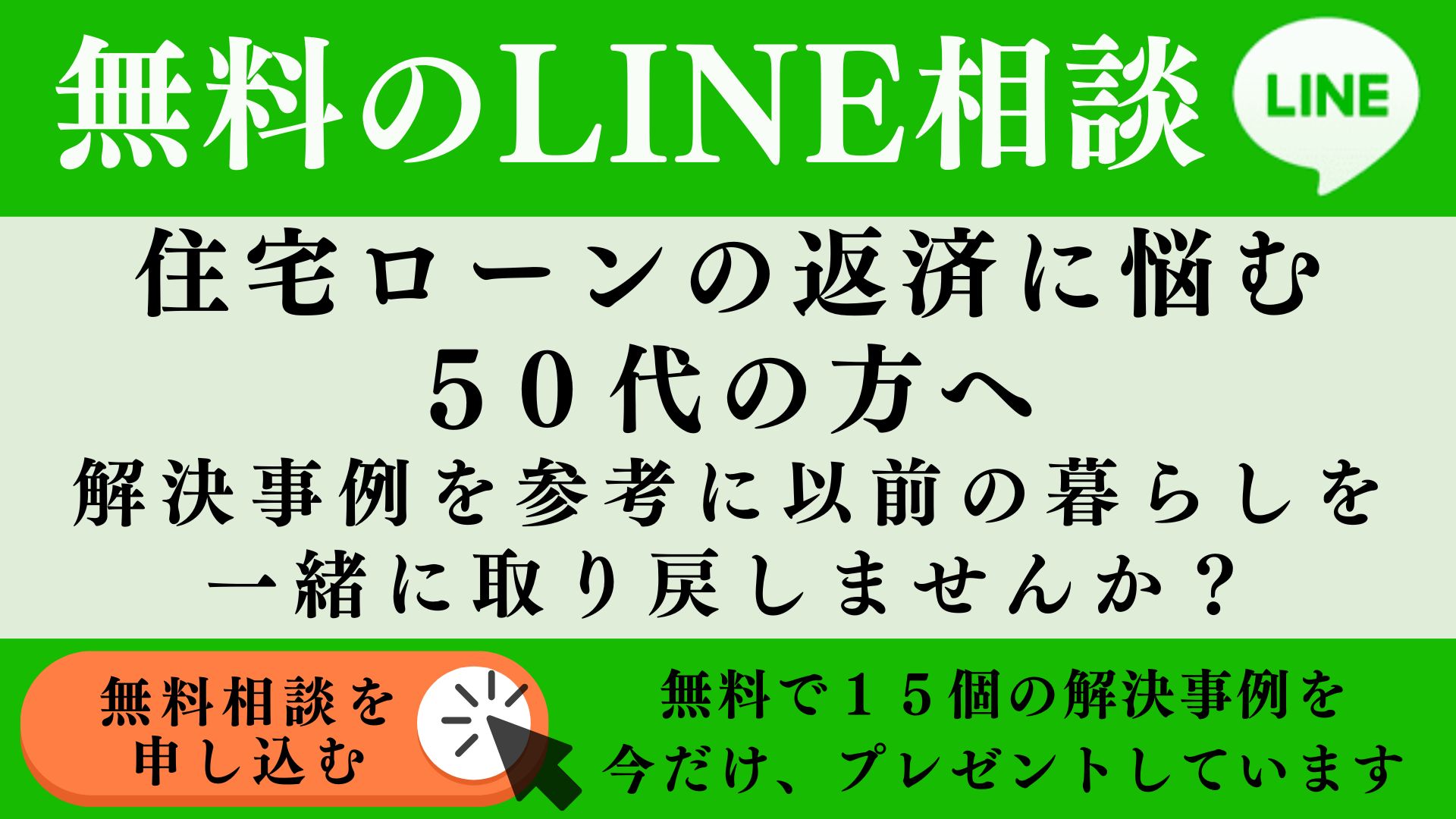
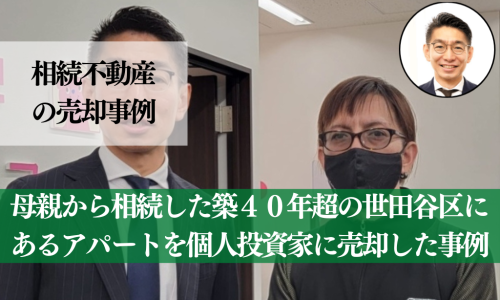
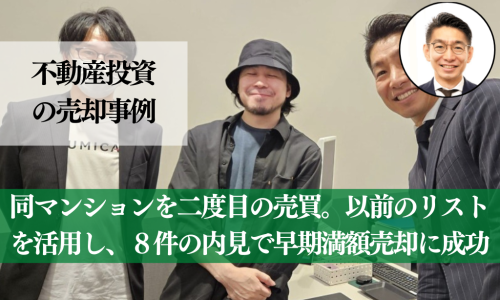
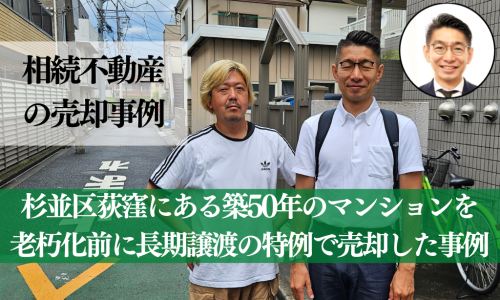

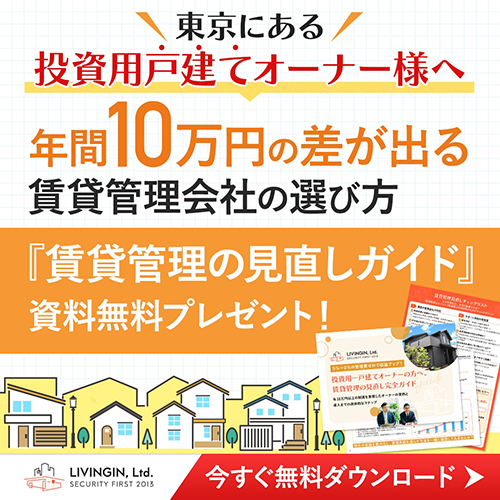
この記事へのコメントはありません。