目次
こんばんば、六本木で取引の不安ゼロを目指す不動産屋、(株)リビングインで建物管理やトラブル解決を担当している不動産鑑定士補兼宅地建物取引士の相樂です。
分譲や賃貸共に部屋探しを始め、スーモで検索していたら、マンションの最上階の部屋が募集に出てくる。タワーマンションを中心に、最上階の部屋はペントハウスなどそれ以外の部屋と圧倒的に差があると言われています。

ここでは、せっかくの引っ越しで大金をムダにしないため、失敗談と口コミを参考にマンションの最上階に住むメリット・デメリットや実際のお部屋事情を解説していきます。
最上階の夏場は屋上からの暑さがキツイと言うのは本当なのか?逆に、暑くならない最上階の部屋はあるのか?そして、最上階はその希少性からステータス重視になりがちで価格以上のメリットってあるか?
スーモを使って、初期費用を下げたい人向けにどれだけ、お部屋の選択肢が減ってしまうか?なら、スーモはどう使うのが良いのか?件数を基に住環境のいい部屋を賢く見つける方法をこちらのページにまとめました。物件数ナンバー1でも絞る条件次第では本当に変な部屋が残ります…。
1.最上階の部屋のイメージ

「最上階の部屋」は一般的に高くてハイステータスで良いイメージと言われていますが、実際はどうなんでしょうか。具体的な巷のイメージをいくつか挙げて考察してみます。
1-1.家賃が高い
最上階の部屋というと、なんとなく「家賃が高い」イメージがあります。同じマンションであっても、最上階が最も高く、1階が最も安いイメージです。しかし、なぜ高いのか、という理由まで正確に理解している人は実はあまり多くなく「なんとなく」とか、「ステータス的に高い」などと思われているようです。
1-2.勝ち組が住んでいる
家賃が高いイメージからも、最上階に住める人は「勝ち組」つまり、「金持ち」や「良い会社勤め」や「資産家」などのイメージが強いです。特に、タワーマンションの最上階ともなると、それだけでステータスとして自慢できるくらい多くの人の憧れの的となります。
1-3.エレベーターが止まったら大変そう
圧倒的にニュースの影響ですね・・・。最上階は「リッチ・お金持ち・勝ち組・高い」というイメージがつきものですが、より現実的に考える人にとってみると、ひとつ「エレベーターが止まったら大変だろうなぁ…」というイメージが沸いてきます。
時々、エレベーター無しのアパートやマンションで4階建て、5階建て、という物件がありますが、このような物件において最上階は「リッチ」から一転、「大変そう」というイメージに早変わりします。エレベーター無し物件の場合は最上階であっても階下の部屋より家賃が安いこともありますし、このイメージの差は大きいと言えます。
エレベーターがしっかりついているマンションであっても、「故障や事故、災害でエレベーターが止まったら大変だろうな」というイメージがあります。
1-4.最上階のイメージはフワッとしたものが多い
最上階のイメージは、プラスのイメージとしては「勝ち組が住むリッチな部屋」や「ステータスが得られるような憧れの部屋」というものがあり、マイナスのイメージとしては「家賃が高い」や「エレベーターが壊れたら大変そう」というものがあります。
しかし、なぜ最上階になると家賃が上がり、リッチでハイステータスなイメージになるのか、という具体的な理由までちゃんと分かっている人は少なく、フワッとしたイメージだけが先行している傾向にあります。
ちなみに、4,600件の引っ越し事例から部屋探し2回目以下の方に特に注意してほしい部屋探しの条件に付いて、こちらのページにまとめました。件数が多かったので、分析に時間が掛かってしまいました…、ごめんなさい。
2.最上階の部屋はどんな人に向くのか?

最上階のイメージが「リッチ」や「勝ち組」、あるいは「ハイステータス」だとしたら、一般庶民には向かないということなのか、というと、そういうわけではありません。なぜ高いのか、どのようなメリットがあるのか、という点をしっかり理解しなければ、自分にとって最上階の部屋が向いているか向いていないかということは分からないです。
「勝ち組」のイメージを手にするために最上階の部屋に入居して、思わぬデメリットに後悔したり、逆に「高い」というイメージで最上階に手を出さなかったことにより後から「やっぱり最上階にしておけば良かった…」と失敗を実感したりすることもあるのです。
本記事では、なぜ最上階は家賃が高い傾向にあるのかという根本的な理由をしっかりと解説した上で、最上階のメリットとデメリットについて徹底解説します。その他、最上階特有のトラブル事例もご紹介し、どんな方に最上階が向いているのか、最上階の部屋を選ぶ時に注意すべき点などについても伝授します。
部屋探しで失敗して後悔しないためにも、自分が「最上階の部屋に向いているのか否か?」という点を意識しながら、最後まで読んでみてください。
3.最上階の部屋のメリット・デメリットと違いまとめ

それでは早速、最上階の部屋のメリットとデメリットについて解説していきます。ここで「なぜ家賃が高いのか?」という理由もメリット共に具体的に紐解いていきますので、よく読んでください。最後には、最上階の部屋とそれ以外の部屋の違いもまとめました。
3-1.最上階の部屋のメリット
最上階の部屋のメリットを下記5点にまとめました。最上階の部屋全てに当てはまるわけではありませんが、このようなメリットを有している傾向にあります。
3-1-1.自由度が高くワンランク上の造りも
最上階の部屋の家賃が高い傾向にある最大の理由が、この「ワンランク上の造り」です。最上階は、階下の部屋と比べて自由度が高く、ルーフバルコニーが設置してあったり、窓の高さを大きく取ってあったり、天井に小窓がついていたり、といった階下の部屋には無い特徴が見られる部屋もあります。
また、最上階は、階下の部屋よりも部屋割り数が少なく、1つ1つの部屋の間取りを広く取っているところも多いです。これにより、最上階の「特別感」を出して家賃を引き上げるとともに「勝ち組」や「リッチ」そして「ハイステータス」といったイメージを強く植え付けています。
実際、広くのびのびと快適に過ごせる間取りになっている部屋は多く、特別感を享受しながら生活できる物件が多い傾向にあります。
3-1-2.上階の騒音が無い
最上階は、当たり前ですが上の階には部屋が無いため誰も住んでいません。マンションやアパートで暮らす上で気になるのが上下左右の住人の生活音です。特に上の階から天井越しに聞こえてくる「足音」が気になるという人は多く、それが騒音トラブルの元になるケースも多いです。
最上階に住めば、当然天井から足音が聞こえてくるという心配は無く、快適に暮らすことができます。下の階の音は上の階には伝わりにくいため、上下の騒音は大分カットされます。
最上階の角部屋であれば、左右どちらかの部屋の生活音からも解放されるため、隣人たちとの騒音トラブルによるストレスリスクを大幅に抑えることができます。
ただし、ひとつ気を付けなければならないことは、階下の部屋に自分たちの足音は聞こえてしまっている可能性があるため、こちらがトラブルの加害者にならないよう注意する必要があります。
特に自分たちは天井から足音が聞こえないため、実際「上の階の人の足音がどの程度漏れ聞こえるのか」という感覚が掴めずに生活してしまう恐れがあり、それが騒音トラブルを引き起こしてしまうリスクにつながります。
>>実際に騒音トラブルに遭い、管理会社や警察に相談した方にヒアリングを行い、こちらにページにまとめました。
3-1-3.高い程、圧倒的な開放感や日当たりが
周辺の建物の高さや周辺環境によりますが、周りに高い建物が無ければ開放感と日当たりを思う存分享受できるのが最上階の良いところです。特に、最上階の角部屋であれば、2方面に窓を確保できるため、マンションの中でも最高の日当たりが得られます。
上階に部屋が無く、従って上階のベランダも無いため、広く開放感のあるベランダを設置することができ、ルーフバルコニーなど階下の部屋ではできないことができるのも最上階ならではのメリットです。
ただ、角部屋ではなく中部屋の場合は角部屋よりも自由度は下がります。しかし、そもそもの間取りが階下の部屋よりも広く取れるような設計であれば、広々とした窓やベランダを確保できる可能性もありますので、実際のマンションで確認してみるのがおすすめです。
3-1-4.防犯面が強く、プライバシーも守りやすい
ちょっと前に、タワマンで強盗がニュースになりましたが、一般的に最上階は1階と比べて圧倒的にセキュリティが強いです。また、通過階にある部屋は、様々な住人や訪問者が廊下などを行き来しますが、最上階はその階の住人か、その住人に用がある人しかやって来ないため、プライバシーも確保されます。エレベーターも最上階の人向けに作られている場合もあります。
1階や2、3階あたりまでだと、地上から窓の中の様子やベランダの様子が見えてしまいますが、最上階ならばその心配の無いため、そういった意味でもプライバシーを守りやすい環境です。歩道橋から部屋が丸見えってこともなくなると思います。
また、建物によっては最上階をリッチな造りにして付加価値をつけるために、特別セキュリティを敷いている物件もあります。最上階にしかつながらず、最上階の部屋のキーが無いと使用できないエレベーターが設置してあったり、最上階のエレベーターホールから廊下へ出るためにキーが必要な仕様になっていたり、いわゆるVIPたちが暮らすための特別なセキュリティで守られた空間になっている建物もあるのです。当然家賃はその分高くなりますが、安全には変えられないため、芸能人や著名人はこのような特別な部屋を借りていることが多いです。
3-1-5.資産価値が高くステータスとなる
最上階のイメージと直接結びつくメリットですが、最上階は高い部屋が多いため、それはそのまま資産価値の高さを意味しています。最上階はその希少性から家賃が高いものの人気も高く、売りに出せばすぐに買い手がつきます。逆に、1階はセキュリティ面やプライバシーの面で人気が低く売りに出したり、賃借人を探したりしてもなかなか見つからないことが多いです。
もっとも、これは賃貸ではなく購入した際のメリットとなりますので、賃貸の場合は次に入る人が見つからずともいつでも解約できますが、賃貸であってもそのステータスを享受できるのは魅力的と言えます。
やはり世間的なイメージとしては「最上階に住んでいる=勝ち組、リッチ、ハイステータス」というものが根強いため、このステータスを得たいという方にも最上階はおすすめです。
3-1-6.背伸びをすることでのメリットも
年収に到底見合わない物件に住んでしまっては、最低限の生活ができなくなり、自分の首を絞めることになるのですが、背伸びをすることによって仕事を頑張ることができるという方には、あえて高めの家賃設定の賃貸に住むこともアリだと思っています。
無理な借金はいけませんが、“男はローンをしてなんぼだ“と昔上司から昔々、言われていたことを思い出しました。
自らお金がギリギリの生活に持っていくことで、もっと余裕のある暮らしをしたい、出世したいと思うようにできる方には背伸びした物件を選ぶことも選択肢に入れてみてください。
3-2.最上階の部屋のデメリット

続いて、最上階の部屋のデメリットについて4つにまとめました。最上階のデメリットというと、イメージとしては「家賃が高い」や「エレベーターが止まったら大変そう」といったものぐらいでしたが、他にもあまり知られていないデメリットがあります。
このデメリットをしっかり押さえておかないとイメージだけで最上階に決めてしまったことにより後悔してしまう可能性が高くなりますので、よくチェックしてください。
3-2-1.家賃が高いことが多い
イメージ通り、家賃が高いのはデメリットのひとつです。高い家賃を払ってでも最上階に住みたい、最上階のメリットを得たい、ということであれば納得できるかと思いますが、少しでも家賃を抑えたい場合はこのデメリットはかなりの痛手になります。
家賃が高いのには理由があり、階下の部屋よりも自由度が高い、セキュリティやプライバシーの観点で安心、開放感がある、などのメリットがあります。これらのメリットと家賃の高さを天秤にかけて、どちらを取るか熟考するのが賢明です。
家賃があがるということは、その他にも入居するときの初期費用や更新費用が高くなり、光熱費や管理費も上がってきます。また、家賃が上がる為、貯金や買い物できる自由なお金が確実に減るため、毎晩飲み歩いて帰っては寝るだけという生活を送られる方にはもったいない選択になってしまいます。
3-2-2.外気温がダイレクトに影響し、夏は暑く冬は寒い
最上階のデメリットとして一番大きいのが、この「夏暑く冬寒い」です。外気温の影響を受けやすい上に、高度が高いため夏の日差しに近く、冬は上空を吹き荒れる北風がモロに吹きつけるため、夏はものすごく暑くなり、冬はとてつもなく寒くなります。
そのため、常時エアコンをつけっぱなしにしなければ快適な暮らしとは縁遠くなってしまい、家賃が高い上にエアコン代まで相当かかってしまうということになります。
金持ちならば「そんなのエアコンつけとけば一発解決じゃん」と軽くあしらえるような問題ですが、背伸びして無理して最上階に住もうとすると、後々自分の首を絞めることとなります。
3-2-3.エレベーターのストレスがつきもの
「エレベーターが止まったら大変そう」という最上階のデメリットイメージはありますが、止まらなくても、通常通りの運行状態であっても、最上階にはエレベーターのストレスがつきものです。
エレベーターの性能にもよりますが、最上階が高ければ高いほど、エレベーターが1階に到着するまでにかかる時間が伸びます。そして、最上階が高ければ高いほど、途中階が増えるため、止まる階も増えます。すると、呼んでもなかなか来ない、乗ってもなかなか着かない、というストレスと直面することになります。
1階ならば当然エレベーターを使うことはないため、マンション(アパート)に到着してすぐに自宅に入ることができます。2、3階ぐらいであれば、エレベーターを使うより階段を使った方が早い!ということで、荷物が軽く健脚であれば階段を使ってタッタカ自室へと向かうことができます。
しかし、最上階の場合は、階段を使って上るとなるととても大変ですので、エレベーターを待つより外ありません。なかなか到着しないエレベーターを待つイライラや、急いでいる時に悠長に動くエレベーターのスピードへのイライラに悩まされることも予想されます。
帰宅時だけではありません。朝寝坊して猛ダッシュで会社へ向かわなければならない、電車に間に合わない、といった切羽詰まった状態であっても、エレベーターを待たなければならないのです。
その上、万一エレベーターが故障したり、修理や点検などで一時的に動かなくなっていたりすれば、階段を使わなければなりません。最上階の階数にもよりますが、高ければ高いほど大変です。
3-2-4.災害時に影響を受けやすい
2019年の大雨や2011年の大地震など、日本では様々な災害リスクが身近にあります。地震、火災、台風などです。実は、この全ての影響を最上階は受けやすいと、知っていましたか?
まず、地震は高い建物の場合、上へ行けば行くほど「揺れ」が大きくなります。建物の倒壊を防ぐために揺れる力を逃がすため、構造上の現象なので必要になってきます。しかし、この「揺れ」が大きくなると、体感として怖さが倍増するのと、家具が散乱しやすく、ガラスが落ちて割れて怪我のもとになったり、落下物が当たり怪我のもとになったり、といったリスクが高まります。その為、最上階を含め、20階以上の部屋に住む場合には、火災保険だけでなく、地震保険や家財保険もキチンと入っておいた方が良いと思います。
続いて、火災です。火や煙は上へ上へと昇っていきます。階下で出火した時には、それよりも上の階にいる人は逃げ場を失い追い込まれやすく、救助を待つしかない、という状況に陥る可能性もあります。非常階段や非常口、非常経路がしっかりと備わっている物件を選ばないと命を危険にさらしてしまうこともあるため、最上階の部屋に住む際には非常時の避難方法はしっかりと確認すべきです。
そして台風は、風の影響です。台風の風は上空の方が地表近くよりも強くなるため、最上階はその強風の影響をモロに受けます。地震でもないのに部屋が揺れることもありますし、窓ガラスに物が当たり割れてしまうリスクも高くなります。
2019年に武蔵小杉のタワーマンションへの浸水でエレベーターを含め停電が起こり、生活できない状態になったのは有名な話です。タワーマンションの最上階まで階段で上がることは現実的には考えづらいですが、実際に起きているので、災害には要注意です。
このように、災害時の影響を受けやすいのも、最上階特有のデメリットです。
3-3.最上階の部屋ではない部屋との違いまとめ
以下、失敗談を参考に、最上階の部屋と最上階以外の部屋の違いをまとめました。
・部屋割り数が少なく間取りを広く取れる、ルーフバルコニーを付けられ、ベランダを広く取れる、窓を大きく取れる、など階下の部屋と比べてリッチな仕様になっている部屋が多く、そのため家賃が高い傾向にある。
・セキュリティやプライバシーの観点で見ると人から見られにくいため安心感がある
・天井からの足音騒音が無いため快適に暮らせるが、自分たちの足音には気を付けるべき
・周辺環境によっては開放感が得られ、日当たりもしっかり確保できる(特に角部屋)
・災害時にはモロに影響を受けるため避難経路などはしっかり確認すべき
・エレベーターは故障時だけでなく通常運行時にも何かとストレスの元となる
・外気温の影響を受けやすく、夏は暑く、冬は寒くなりがちなのでエアコン代がかかる
こうしてまとめてみると、意外とメリットよりもデメリットの方が目につきます。その為、自分にとって最上階の部屋は本当に必要なのか、最上階ならではのメリットを希望するのか、自分は最上階の部屋に向いているのか、よく考えて検討してください。
3-4.高めの家賃に背伸びをしてもいい人とダメな人
3-4-1.メリットがある人
- 家で過ごす時間を大事にしている方
- 在宅ワークを始めようとしている方
- 人を家に招いて見栄を張りたい方
- 家賃の高さから仕事へのモチベーションを上げられる方
このような方々であればメリットを存分に受けることができそうです。全ての事項が自身のモチベーションを上げることで、自分を高めていこうとする行動が共通しています。そして、逆にデメリットになってしまう方を以下に記載します。
3-4-2.デメリットになる人
- 収入が不安定な方
- 仕事終わったら帰って寝るだけの方
- 趣味にお金を使いたい方
- 近々で引っ越しを考えている方
基本アウトドアが好きで、家にこもっているのが苦痛な人には合いません。家賃を払うよりも、身に着ける時計などにお金を投じた方が価値を発揮できそうです。
また、転職や同棲を考えている方も部屋数が多めに必要になったり転職により収入が下がったりする可能性も考えられますので、生活が落ち着いた時に引っ越すことをオススメします。
4.実際に、最上階の部屋に引っ越した4人のトラブル

私たちが独自におこなったアンケート結果から、最上階の部屋に引っ越した人のトラブル事例を4件ご紹介します。トラブルですので当然デメリットとリンクするものが多いのですが、このような実際のトラブル事例をご覧いただくことで、先ほどご紹介したデメリットの信ぴょう性を確かめていただけます。
4-1.事例1:階下の住人からの騒音の苦情
1件目の事例は、階下の住人との騒音トラブルです。入居したマンションは4階建ての最上階でしたが、階下住人から「子供の足音がうるさい」との苦情は2回ありました。最上階のメリットとして「天井からの足音などの騒音が無い」という点を挙げた際に、「ただし自分たちの足音は階下に聞こえてしまうため要注意」と書きましたが、まさにそのケースです。
特にお子さんがいらっしゃると、ドタバタ走り回ったり、有り余る元気でジャンプしたり、取っ組み合いのケンカをしたり…ということもあると思うので、このような苦情が出たことが予想されます。
自分たち(あるいは子どもたち)の足音を気にせずに暮らしたいという場合は、逆に階下からのクレームの可能性が無い1階の方がおすすめのケースもあります。ただ、小さなお子さんがいる場合はセキュリティのことも考えると難しいところですが…。
いずれにせよ、最上階で暮らす際には、少なくとも「このぐらいの足音を立てると下の部屋に響く」という基準だけでも知っておいた方が良いと言えます。
4-2.事例2:夏の暑さと冬の寒さでエアコン代がかかる
2件目の事例は、暑さ・寒さ問題です。最上階だったので、寒暖の差が大きくエアコン代がすごくかかってしまいました。まさに、デメリットで挙げた通りの内容です。アンケートでは、この方以外にも複数の声が挙がっており、最上階は寒暖差が大きくエアコンは無くてはならない必須アイテムだったということが分かりました。
4-3.事例3:エレベーターのストレス
3件目の事例は、エレベーターのストレスについてです。勤務先が駅近くでマンションも徒歩で5分以内の場所としました。いわゆる駅裏のオフィスエリアにて夜は静かになり、コンビニや飲食店も適度にあり便利でした。ところがマンションのエレベーターが1基しか無く、最上階だったため毎朝エレベーター待ちでイライラすることになり、戸数とエレベーターの数まで確認しなかったことが原因です。
戸数が多くエレベーターが1基しか無い、など、バランスが取れていないと、エレベーターの利用者が殺到する通勤ラッシュ、通学ラッシュ時にはなかなかやって来ないエレベーターにイライラさせられそうです。
最上階で暮らす際には時間に余裕を持って行動することを心掛けなければならないので、ついギリギリになってしまいがちな人には向かないかもしれません。
4-4.事例4:雨漏りトラブル
4件目の事例は、雨漏りです。最上階だったのですが、ある日突然雨漏りがして天井に水溜りができ、部屋に漏水するということがありました。屋上から漏れてきたようです。
これはデメリットでは触れませんでしたが、確かに最上階ならではのトラブルです。
(上階の水漏れによる漏水トラブルは最上階以外の部屋でも起こり得ますが…)
雨漏り被害は建物そのものの問題となるため、修繕費や原状回復費を自己負担しなければならないということはありませんが、雨漏りによって大切な私物が濡れてしまったとしたら、それは大問題です。
最上階には、このようなリスクもあると頭の片隅に入れておいた方が良さそうです。
5.最上階の部屋を選ぶときの注意点

最上階の部屋と一口に言っても、様々な部屋があります。メリットの部分が大きく、デメリットの多くがカバーできている部屋もあれば、その逆も然り。最上階の部屋を探す際には、どのような点に注意すべきか、まとめました。
5-1.最上階以外の部屋との違いやメリットを確認
最上階の家賃が高いのには理由があると解説しました。最上階だから高いのではなく、最上階の部屋の造りが他の部屋とは違うから高い、あるいはセキュリティが強固だから高い、など、家賃が高いのには必ず理由があります。その理由をきちんと確認せずに「最上階だから高いよね、仕方ないよね」と納得しない、これが大事です。
最上階以外の部屋とは何が違うのか、その違いから得られるメリットは何なのか、この部分をしっかりとチェックして、その違いと家賃の差が納得できるものかどうか吟味することが大切です。
5-2.周辺の建物の高さや周辺環境をチェック
最上階は開放感がある、最上階は日当たりが良い、これらは周辺に高い建物や日差しを遮るものが無いという前提条件のもとで成り立つメリットです。
部屋の間取りや内装だけでなく、必ず周辺環境も確認しなければなりません。最上階の部屋よりも高い建物がすぐ近くに経っていたり、南側に日差しを遮るような大きな建造物があったりしたら、そこはおすすめとは言い難いです。
5-3.最上階ならではの特徴が自分の希望とマッチしているか精査
最上階の部屋特有のメリット、特徴については解説の通りです。部屋割りが少なく、間取りを広々取れる、ルーフバルコニーや広いベランダなど、階下の部屋では実現できない造りになっている、採光状態が良い、開放感がある、天井からの騒音リスクが無い、などです。
これらの最上階ならではの特徴が、自分の希望とマッチしているかどうか、これは建物の吟味というよりも、自分自身の心と向き合うことですが、しっかりと精査するのが大事です。
ただ営業マンの言葉に押されて「なんか良い部屋っぽいから、ここにしよう」と決めてしまうと、最上階の部屋ならではのメリットの恩恵をそれほど自覚できずに高い家賃だけ払い続けることになってしまいます。結果的に、特にこだわりがないのであれば、何も最上階の部屋にする必要はないのです。
5-4.セキュリティ面や災害時の安全性を確認
散々書いてきたことですが、非常に大事なことなので、何度でも書きます。最上階は災害の影響を受けやすいため、避難階段、避難経路、避難方法についてはしっかりと確認しなければなりません。これについて確認した時の返答が曖昧だったり、しっかりとした避難経路を提示されなかったりしたら、その物件はおすすめしません。
また、セキュリティについて重視しているのであれば、最上階ならではのセキュリティ強化ポイントはあるのかどうかも併せて確認しておくと良いです。
5-5.夏の暑さや冬の寒さを担当に確認
部屋の内覧は基本的には1回(または数回)しかできません。その時の季節、時間の部屋の状態しか知ることができないため、夏や冬の温度については、担当に確認しておく必要があります。
「最上階は寒暖差が大きくて、夏は暑く、冬は寒くなるって聞きますが、この部屋は実際どうですかね」といった聞き方で大丈夫です。
「階下の部屋よりは寒暖差が大きい」と言われることもありますし、「機密性にこだわっているからそこまで気にならないですよ」と言われることもあると思いますが、参考までに必ず聞いておくのが賢明です。
5-6.屋上に何があるのかも要チェック
トラブル事例で雨漏りの件がありましたが、屋上に何があるか確認しておくのも忘れないようにしてください。今はほとんど見かけませんが、屋上にプールがついていたり、貯水タンクがあったり、というマンションもあります。そうなるとやはり水漏れが心配です。
上の階に住人が居ないからと安心せずに、自分の部屋の上には一体何があるのかということは事前に確認しておくべきです。
6.最上階の部屋で起きた判例は?
最上階に関係する判例はありませんでした。
7.どんな最上階の部屋ならいいか?

最上階の部屋選びで後悔しないためにも、どんな部屋を選べば間違いないのか、そのポイントをまとめました。
7-1.エレベーター故障や災害の影響が怖ければ、高くないマンションがおすすめ
リスクヘッジとして、エレベーターの故障や修理、災害の影響などのリスクをなるべく避けたい、減らしたい、ということであれば、あまり高くないマンションの最上階が良いです。4階か、せいぜい5階ぐらいになります。個人的には、騒音対策に、壁式マンションを選ぶなら、このぐらいの階がお勧めです。
いざという時に、階段から駆け下りたり、駆け上がったりできる階数であれば、エレベーターに何かあった時もどうにかなりますし、災害時のリスクもある程度は下げることができます。
7-2.他の階よりも値段が高くても自分の希望に合っている部屋ならOK
最上階のデメリットは家賃が高めであることですが、家賃はあくまでも「対価」ですので、その対価を支払うだけの価値があると納得できれば、階下の部屋より高くても最上階に住むという選択は間違っていません。
ただ、気を付けなければならないのが「最上階」というネームバリューやステータスのために、安直に決めてしまわないように、という点です。自分の希望に適った部屋なのかどうか、これが見極めるポイントとなります。最上階の部屋である意味は?高くてもここに住むメリットは?と、整理して考えてください。
7-3.騒音リスクを減らしたければ、角部屋がおすすめ
騒音や隣人の生活音を気にするのであれば、最上階の中でも角部屋がおすすめです。角部屋であれば、端の部屋なので隣接する部屋は1つだけになります。角部屋は窓が増える分、家具や家電の配置が問題になってきます。こちらに角部屋のメリット・デメリットをまとめておきました。
上にも住人がおらず、下の階の生活音は上の階にはそれほど響かず、隣の部屋1つの生活音が聞こえるかどうかぐらいになるので、騒音に悩む可能性はかなり下げられます。また、角部屋は窓を多く、大きく確保できるため、日当たりや風通しも良く、開放感が得られます。
角部屋がどんな人に向いているのか、まとめたページはこちらです。
7-4.気密性が高く、外気の影響を受けにくい部屋ならなお良し
最上階のデメリット代表である外気温の影響による寒暖差ですが、気密性が高く外気の影響を受けにくい構造になっていることを売りにしている部屋であればかなり安心です。
エアコンをつけて室内温度を調整するから別に構わない、と言えるくらいにお金に余裕があれば気にしなくても良いのですが、なるべく生活費は抑えたい、ということであれば気にしたいポイントです。
7-5.最上階の中間部屋はメリットを生かせるのか?
最上階の部屋として、角部屋をおすすめしました。騒音リスクも低減できますし、日当たりや風通し、開放感という面で見ても、非常に優秀だからです。
では、最上階の中部屋はどうなのか、これに関しては「何とも言えない」というのが今のところの答えになります。というのも、最上階のメリットである「開放感」や「騒音リスクの低さ」などは、角部屋で真価を発揮するものであり、結局中部屋の場合は両隣の住人の生活音が聞こえてしまったり、窓も1方面にしかつかずに大した開放感が得られなかったり、という可能性があるからです。
もっとも、部屋割りの数を他の階よりも少なくしていれば、間取りを広く取れるため、隣人の生活音が聞こえる率や音量を下げることができますし、最上階ならではの広々とした空間で生活ができるメリットも得られます。
ただ、全ての物件の最上階が部屋割りを少なくして広々取っている、というわけではありません。階下の部屋とほとんど変わらないような部屋も多数あります。こういう場合だと、最上階に住むメリットはあまりない、と言わざるを得ないケースもあるということになります。
最上階に住むなら絶対角部屋!!というわけではないのですが、どこの部屋であっても、最上階ならではのメリットがしっかり得られる部屋なのかどうか、ちゃんと確認するのを怠らないと心に留めておくべきです。
8.マンションの最上階の部屋、まとめ

最上階の部屋について、メリットやデメリット、トラブル事例などを紹介してきましたが、結局のところ、どんな人が最上階に向いているのか、そしてどんな部屋なら住んで良いのか、最後のまとめに入ります。
8-1.分析を踏まえた上で、最上階の部屋に向く人とは?
色々分析してきて、最上階の部屋に向いている人の特徴は下記の通りとなります。
- セキュリティやプライバシーを気にする人
- ワンランク上のラグジュアリー感を求める人
- 騒音トラブルに悩まされたくない人(被害者側として)
- 開放感や日当たりの良さを求めている人(ただし部屋の構造や周辺環境による)
- 勝ち組、リッチ、ハイステータス、と思われたい人
- エレベーターを待ってもイライラせず時間に余裕をもって行動できる人
- 災害時に落ち着いて行動できる人
逆に、パニックになりがちな人、せっかちな人、騒々しい人、とにかく安さを求める人には向かないと言えます。当てはまる項目はありましたか?もし、「最上階に向いているかも?」と思ったら、是非最上階のお部屋を検討してみてください。逆に「なんかイメージで最上階はカッコいい!と思っていたけど自分には向いてなさそう」と気付けたら、それはとてもラッキーなことです。
8-2.どんな最上階の部屋なら住んでいいか?
最上階の部屋探しの注意点でも述べましたが、最後にもう一度復習します。最上階の部屋で選んでも失敗しない良い部屋の特徴は次の通りです。
- 災害時の対策や避難方法がしっかりしている
- エレベーターと戸数のバランスが取れている
- 最上階ならではのメリットがしっかりある
- 中部屋よりも角部屋の方がおすすめ
- できれば気密性が高く外気の影響を受けにくい部屋が吉
最上階の部屋を検討する際には、失敗しないために上記5つのポイントを意識して、担当に質問したり内覧の時に注意して確認したりするよう心掛けてください。
失敗の無い部屋探しをするためには、何も考えずにただ感覚だけで決めるのではなく、しっかり下準備をして、下調べをして、自分なりに希望やこだわりを整理しておくのが重要です。どうやったら良いか分からない時にはプロの力を借りてください。いつでもご相談をお待ちしています。
内覧でいかに真剣に部屋と自分と向き合ったかということが部屋に住み始めてから後悔するかしないかを決定づけます。是非、是非、失敗や後悔の無い部屋探しをしてください。今回ご紹介した内容が貴方の失敗を防ぐ一助となれば幸いです。
あなたの大切な人生と平穏が守られますようにこれからも私たちは4,500件を超える引っ越しの失敗談を基に、住まいのトラブル解消の専門家として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。
今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

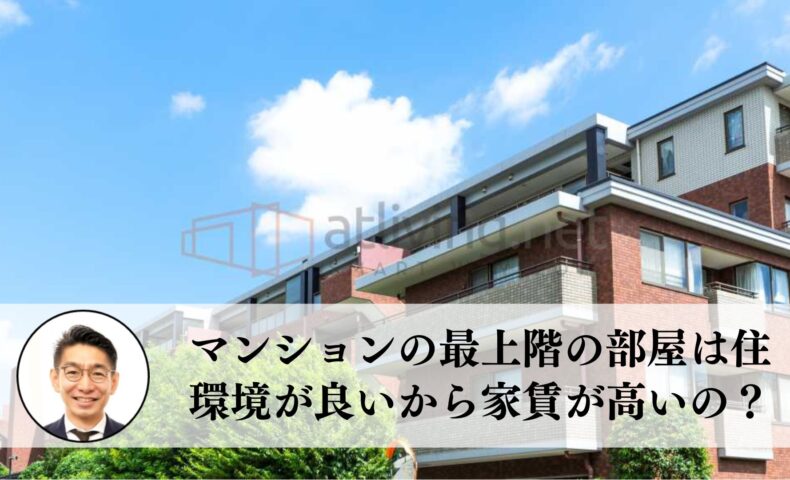




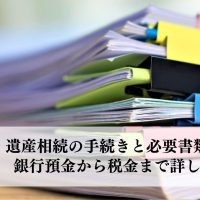

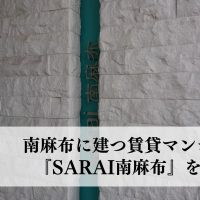

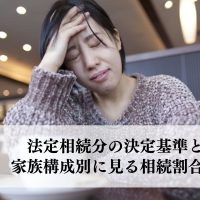



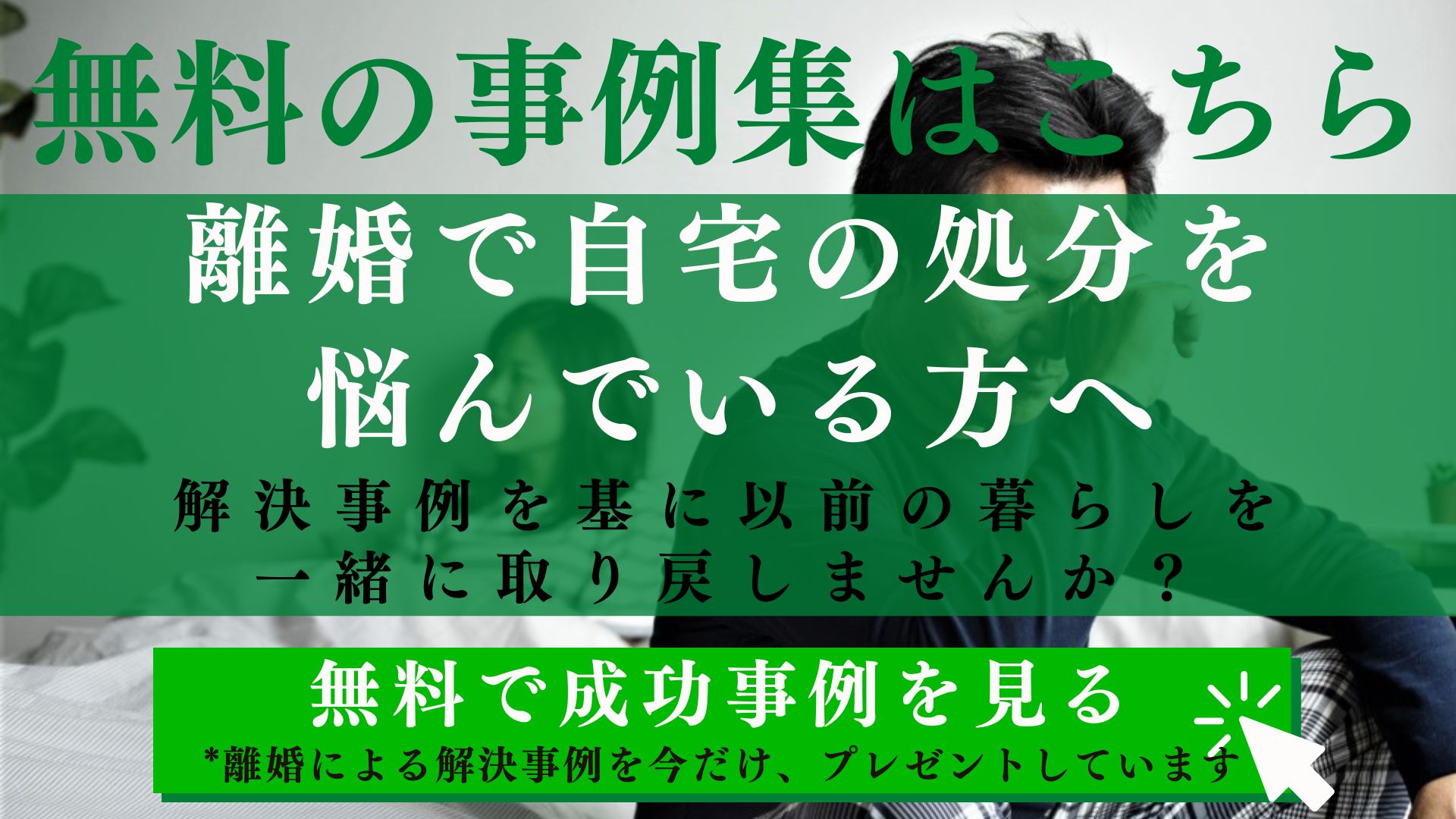
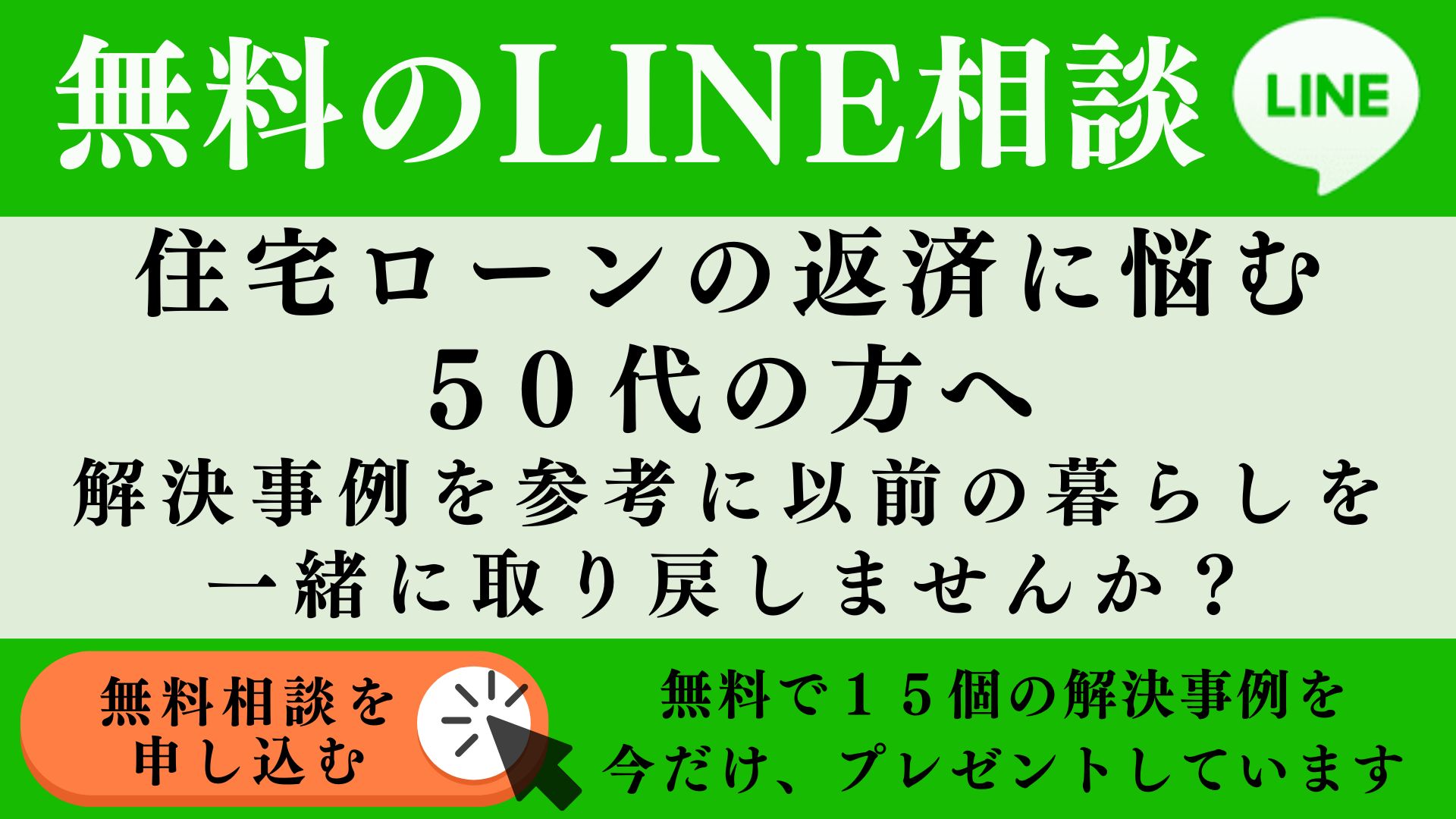
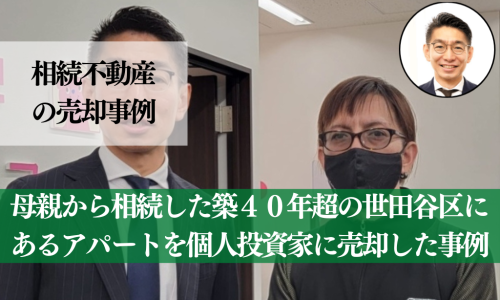
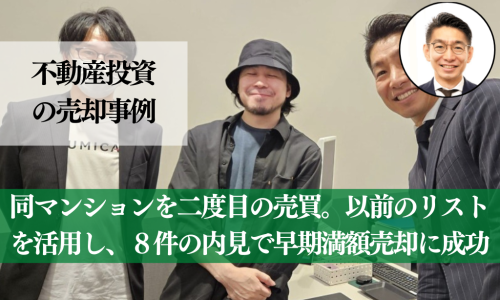
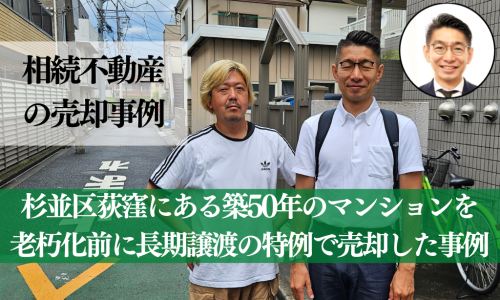

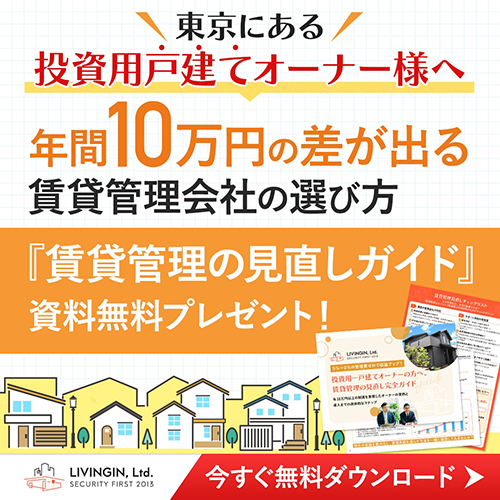
この記事へのコメントはありません。